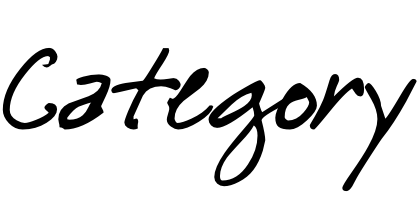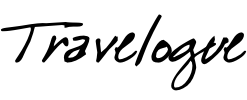 僕らの新しいローカリズム
僕らの新しいローカリズム

僕らの新しいローカリズム|石川 能登
半島という地形は魅力的だ。独立しているようでいて地は続き、
吹き抜ける風が、海の向こうから運んで きた種を落とす。
日本海に最も突き出した半島、能登。
北前船や京文化が種を落としたこの土地では、今また新しい人、戻る人、迎える人がひとつになって食文化の芽を育てている。
山から海へと巡る食、蔵と田が醸す酒、昇華された工芸品。
「能登の自然は時に厳しいけれど、それを癒やしてくれるのもまた自然」
傷ついた人々にさえそう感じさせてしまう、能登とはどんなところだろう?
写真/伊藤徹也 文/井川直子
CHAPTER 23『Villa della pace(ヴィラ デラ パーチェ)』後編
能登というチームの力
『
Villa della pace
』のテーブルに着くと、土地の植物が漉き込まれた
能登仁行和紙
が一枚。その冒頭には、時候の言葉が添えられていた。
たとえば取材時、4月の初めはこんな一文だ。
「若芽色/山が冬の眠りから覚め、木々や草花の芽吹きが日毎に山の景色を替えていきます。山から生まれる新しい生命が、私たちの冬を乗り越えた身体を作り変えていくような感覚を覚えます。」
芽吹きゆく能登の山を思いながら、文字を追う。すると今度は、謎解きのヒントみたいな単語の数々。
「牡蠣 明日葉 青海苔」「畑」「クエ 春キャベツ アスパラガス」「七面鳥 新じゃが」……。
妄想を掻き立てるようなメニューにわくわくしながら、ふと裏面を見て、さらに驚いた。
料理に関わる食材の生産者、器やカトラリーの作家、空間を創り上げた職人たちの名がびっしりと刻まれているのだ。
野菜、七面鳥、牛乳、ジビエ、卵、パン・コンプレ、刺網漁、宝連葛、漆器(塗師、木地)、ステーキナイフ、陶器、硝子、設計、壁紙……。この日ならば32組。本当にびっしりと。
「僕ひとりで完結する料理じゃない」
平田明珠(めいじゅ)シェフの言葉に、あらためて、能登という半島の特別さを思う。季節の移り変わりが早い山、真逆の性質を持つ内海と外海、生活に根ざした人の技巧。
たしかに『Villa della pace』の皿は、能登のチーム力に支えられている。けれど半島に点在する宝を見つけ出し、ガストロノミーという表現に磨き上げる人がいなければ、やはり完成しない料理である。
なんでこんなものが欲しいの?
能登のチームを知りたくて、生産者を一人紹介してほしいとお願いすると、「一人は難しいなぁ」と平田さんは悩んでしまった。
たとえば農家でも、野菜、ハーブ、エディブルフラワー、穀物といった作物の種類ごとに得意な生産者がいて、同じ種類でも今の時季はこの人、といった違いもあるからだ。
しばらくして、『
ほんたに農園
』本谷宏志さんの名が挙がった。年齢も近く、お互いに勉強し合いながら歩んでいきたい生産者だという。
「環境に負荷のない方法で栽培されていますが、いいと思ったら取り入れる柔軟な方。偏りすぎない考え方にも共感しています」
平田さんより3つ年上の本谷さんは、1983年に七尾市中島町で生まれ、同じ石川県の小松市で育った。
大学から県外へ出て、卒業後は滋賀県の生産者のもとで野菜作りを学んだ後、30歳の時にこの七尾市へ帰郷。
地元の集落営農に就職したが、結婚を機に独立。現在は野菜の種類や品種の選定、自分たちの栽培方法などを、妻の亜以里(あいり)さんと二人で研究している。
その一つが、彼いわく「マニアックな肥料屋」から取り寄せる有機肥料だ。
海藻、魚かす、鰹節粉、昆布のかすなどを配合してあり、アミノ酸が豊富なのだそうだ。見せてもらうと、袋を開けた途端に「だし」の香りがした。
夫妻の畑は、『Villa della pace』と同じ七尾市中島町に、いくつか点在している。本来なら茄子やパプリカ、ブロッコリー、かぼちゃなど一般的な野菜がメイン。のはずだが、気づけばケールにスイスチャード、オクラの“花”など、平田さんのリクエストで新しい作物もじわじわと増えている。
「いやぁ、なんでこんなものを欲しがるの?と思うことがよくあります」
たとえばあえて遅い時期に収穫する、硬くなったえんどう豆。
平田さんは「豆板醤を作るので、どれだけ硬くてもいいです」と言う。本谷さんとしては、やわらかいうちに収穫したい本能を抑えて、豆板醤用に少し残しておくのだそうだ。
「遅れないように採るのが基本なんですけどね(笑)。そういう、(生産者の常識からすれば)ちょっとおかしなことばっかりというか、野菜の使い方に関して、彼は“変態”ですよね」
びっくりしておもしろがって、新しいことに挑戦してくれる相棒は、料理人にとってどれほど心強い存在だろう。そんな感じで、本谷さんは農家なのに、野生の鬼胡桃から樹液を採取する担当にもなっている。
桜仕事に鰯仕事、忙しい季節の仕事
レストランで、鬼胡桃の樹液や豆板醤?
そう『Villa della pace』では、その時季に穫れる食材でさまざまな調味料や保存食を自家製し、それらを料理に活かしているのだ。
塩漬けに醤油漬け、味噌漬け、粕漬け、酢漬け、オイル漬けといった“漬け物”系は数知れず。パウダード(乾燥粉末)、発酵醤油、ヴィネガー、ビーガンバターなどの調味料もオリジナルが多く、厨房はまるでラボのよう。
たとえば桜の花が咲いたら、平田さんは「桜仕事」で忙しくなる。八重桜、上水桜(ウワミズザクラ)といったいくつかの種類ごとに分けて仕込む桜の塩漬け。
生で食べられるほど新鮮なアスパラガスも、いっぺんにたくさん穫れる旬には浅漬けになる。ぬか床ならぬ“パン床”は、パンの端切れに水を加えて発酵させたもの。季節ごとの野菜が一年中、何かしらこの床で眠ることになる。
山に行けば、河内地区なら河内豆(黒い大粒のインゲン豆)という、集落だけに伝わる在来種がある。地元の人が乾燥して保存し、炊いて食べたように、平田さんは乾燥豆を赤ワインとみりんで甘酸っぱく炊いて保存する。
海ならば、3月は「鰯仕事」のシーズンだ。
「七尾湾の定置網に、すさまじい数の真鰯がかかるんです」
こちらはイタリアの仕事を施し、1年分のアンチョビになる。塩漬け後、平田さんはオリーブオイルでなく米油に漬けている。
季節、といっても能登の移り変わりはピッチが細かい。芽が出た、花が咲いた、終わりそう、など自然のペースにつき合って作る、季節の仕事は常にある。
揚浜式の塩で作る、塩むすびの味
『Villa della pace』は自家製調味料の多いレストランだが、代えが利かないのは「塩」。平田さんが愛用するのは、奥能登の珠洲市大谷地区に製塩所を構える『中前製塩』の「大谷塩」だ。
「複雑な味でいて、雑味や角がなく、主張もしない。純粋に旨みの深い塩です。素材の繊細な風味を生かしたいと考える、僕の料理には欠かせません」
しかし珠洲市は、2024年1月の能登半島地震で最も被害の甚大だった地域である。『中前製塩』の中前賢一さんは、自宅の倒壊により亡くなられた。享年77歳。跡を継いだのは、夫とともに山形県でラーメン店を営む、三女の阿部良枝さんだ。
「継ごうと思えたのは、父と一緒に塩づくりをしていた上谷(かみや)達也さんが“続けたい”と申し出てくれたことが大きいです」
『中前製塩』は同年4月から塩づくりを再開。しかしそこへ同年9月の集中豪雨が襲いかかった。山が崩れて土砂が塩田に流れ込み、タンク置き場の床も抜け、塩をつくることができなくなってしまった。
2025年4月、再び立ち上がろうとしている『中前製塩』を訪ねた。夏頃の再開に向け、上谷さんが一人で、できる範囲の準備を整えている。
「地震では海底が隆起して、海岸線が50メートル遠くなったんです」
地形を一瞬にして変えてしまう、揺れを想像して足がすくんだ。見れば足元のコンクリートも大きくひび割れている。けれど、泥だらけになったと聞いていた塩田は、美しく輝いている。
「早く塩がつくりたくて」
上谷さんが手入れをして蘇らせたのだった。
塩田がつやつやと輝いているのは、『中前製塩』では「砂」でなく「砂利」を敷き詰めているからだ。
珠洲市で500年以上も続き、国の重要無形民俗文化財にも指定されている「能登の揚浜式製塩の技術」は、海水を汲み上げて砂地の塩田に撒く。天日で乾かし、塩分の付着した砂を集めて濃度の濃い鹹水(かんすい)を採った後、鹹水を釜で炊くことで結晶化させる。
しかし塩分のついた細かい砂を、炎天下でかき集める作業は重労働だ。
高齢化や人手不足が深刻な時代、この問題を解決しなければ揚浜式の塩が存続できない。そう危機感を持った中前さんは、「砂」を「砂利(小さな石)」に替え、塩田に傾斜をつけて水路を設ける仕組みを考案した。
塩田に海水を撒き、天日に干すまでは同じ工程。ただし砂利ならば、もう一度海水を撒けば塩分だけが溶け落ち、濃縮鹹水となって水路に流れ込む。これならば人間に過度な負担もなく、濃縮鹹水が集められる。
中前さんが製塩業を始めたのは2001年、54歳から。
建築業を営んでいたが、塩の専売制度が廃止された途端、塩づくりにのめり込んだ。子どもの頃に食べていた、揚浜式の塩むすびのおいしさが忘れられなかったのだ。
「父が何度も味をみながら、火加減や温度、時間など試行錯誤していたのを覚えています」
そういう良枝さんもまた、祖母が干した岩海苔を炙って、揚浜式の塩むすびに巻くのが定番だったという。なんと贅沢なおむすびだろう。
生前の中前さんが、上谷さんに繰り返し伝えたことがある。
「(釜を)焚きすぎるな、ということです。沸騰しすぎると結晶が細かくなりすぎてしまって、おいしくないと。辛いだけの塩では駄目、旨みが大事なんだとよく言ってました」
上谷さんは地震で自らも被災したし、豪雨では命の危険を感じるほど恐ろしい体験をした。それでも奥能登に残って、塩づくりを続けると決めたのはなぜだろう?
「なんもやらんで辞めるのは、(中前さんに)怒られると思ったんです」
砂利の塩田に、日本海の海水が撒かれる日はもうすぐだ。

- Villa della pace(ヴィラ デラ パーチェ)
-
能登の風土、歴史、民俗を紐解きながらクリエイトする、「能登饗藝料理(のときょうげいりょうり)」を掲げるオーベルジュ。ソムリエ・塩士卓也さんのセレクトによるワインも素晴らしい。1日1組の客室は2〜4名まで、レストランのみの利用もOK。北陸新幹線・金沢駅からレンタカーを使えば、片道1時間ほどで到着できる。
石川県七尾市中島町塩津乙は部26-1
TEL|0767-88-9017
営業時間|ランチ12:00〜、ディナー18:00〜(一斉スタート) チェックイン16:00〜18:00 定休日|水、木+不定休あり( Instagram または電話に て確認を)
食事|コース19,800円(税サ込)
宿泊料金|1泊2食 付42,000円(税サ込)
アクセス|車/のと里山海道徳田大津ICから約7分、電車/のと鉄道笠師保駅から徒歩15分
NEXT CHAPTER
「僕らの新しいローカリズム」石川県・能登編は全6回。
第3回は、七尾湾の穏やかな海で育まれる『能登かき 宮本水産』。桜の季節に旬を迎えた最高潮の能登かきと、そのおいしさを守る、宮本さん一家の丁寧な仕事をお伝えします。
次回の公開は、2025年9月8日コーンムーン。毎月、満月の日に新たな記事を更新します。
CHAPTER 24 comming soon『宮本水産』