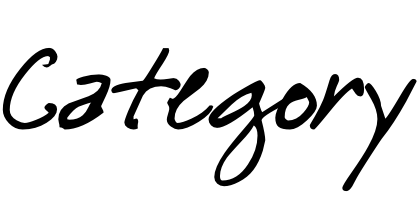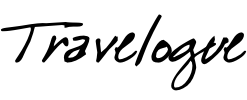 僕らの新しいローカリズム
僕らの新しいローカリズム

僕らの新しいローカリズム
地方が動き始めている。
都市では「食材」や「原材料」と呼ばれるものが
田畑で実り、山に生え、風土の中で生きている場所は、
食べものづくりの人々にとって、刺激に満ちた“現場”なのだ。
ローカルという現場に立つ彼らは今、都市ともゆるくつながりながら
暮らしを映す食や酒、共感で結ばれたコミュニティを生んでいる。
新連載「僕らの新しいローカリズム」、スタートは北海道・函館編から。
石畳の坂道に洋館が建ち並ぶ港町風情と、雄大な自然が静かに溶け合う
この地に惹かれたつくり手たちを、全9回にわたってお伝えします。
写真/伊藤徹也 文/井川直子
CHAPTER 07
『山田農場チーズ工房』
僕らはみんなで、一つの食卓をつくっている
本連載で最初に北海道の函館を取り上げたいと思ったのは、『
山田農場チーズ工房
』を営む、山田圭介さんのひと言がきっかけだった。
「僕らはみんなで、一つの食卓をつくっている」
「食卓」という言葉が、「食文化」にも聞こえた。
函館市とその近郊は、野菜、果実、肉、魚、パン、菓子、ワイン、そしてチーズまでが地元産でまかなえる。自然が豊かなうえ、技術を持った人たちが全国から集まっているからだが、それだけじゃない。
つくり手として、何を大切にしたいのか?
そんな食べものづくりの核心を、函館の生産者や料理人たちはお互いにわかり合い、わかち合い、自分たちの土地を揺り動かしている。
函館市内にあるレストラン『
コルツ
』の佐藤雄也シェフは、『山田農場チーズ工房』のスタート時から15年あまり、彼らのチーズを尊敬し、チーズを主役にした一皿をメニューに載せ続けている。
「熟成させたチーズは酸味もコクもあり、熟成させないフレッシュタイプはすごく緻密な味わい。春から秋にかけて山の環境が変わるにつれ、山羊の食べるものも変わるので、チーズの香りや味がどんどん、どんどん変化するんですよ。お客さんに、その時のその味を楽しんでもらいたくて」
人間と動物が共生していた場所
山田さん夫妻が、生後3カ月の長男と、函館近郊にある七飯町上軍川(ななえちょう かみいくさがわ)に移住したのは2006年のことだ。
2人はともに『
共働学舎 新得農場
』の出身。北海道十勝地方の新得町で、酪農とチーズづくりを中心に営み、国際的なチーズコンテストで数々の受賞歴を持つ農場である。
圭介さんはチーズを、妻のあゆみさんはチーズと酪農を学び、自分たちの牧場を開くための土地を探して道南へ向かった。
「道南は北海道でも独特で、近づくにつれ樹木も山もどんどん風景が変わるんですよ。この植生の豊かさは、チーズづくりにきっとおもしろい影響を与えると思って」
山羊をのびのびと放牧できる山の、陽当たりのいい南斜面が理想。
そうして見つけたのが上軍川だった。活火山の駒ヶ岳と、その噴火によって生まれた湖沼群を擁する大自然、大沼国定公園からすぐの山あいである。
圭介さんによればこの一帯は昔、人間と、牛や馬などの動物たちが共に暮らす土地柄だったという。
けれど、当時は唐松や笹藪だらけの荒れた雑木林で見る影もない。夫妻は広葉樹を残して雑木を切り、開墾した土地に、古くは自生していたとされる野芝の種を蒔き、山羊や羊を放った。
自分たちが暮らす家もDIYだ。ライフラインの水道と電気を引き、廃材を集めて自宅とチーズ工房、動物たちの小屋を建てた。
開墾から17年後、2023年夏。
『山田農場』では山羊たちがふかふかの牧草やどんぐりの実を食べながら、広い斜面を自由に散歩したり、木の切り株の上から跳ねたり飛んだりして遊んでいる。
人懐っこく、笑っているようにも見える彼女らは幸福に違いない。
あゆみさんは、山羊の餌となるはね大豆や雑穀、米のくず米と米糠、ビートパルプ(砂糖大根の搾りかす)などを竈で炊き、毎朝夕には乳を搾る。
圭介さんはその乳でチーズをつくる。
一度は失われた共生時代の原風景が、よみがえっていた。
微生物は、見えなくても感じることができる
夫妻には牧場を開いた当初から、目指すチーズがはっきりとある。
「この土地だから、できるチーズです」
かつてヨーロッパで技術を学び、日本に持ち込んだ先駆者たちは「本場そのままの」「本場に負けない」チーズを追いかけた。おかげで日本には330を超えるチーズ工房が生まれ(2020年農水省調べ)、今や世界的評価も高まっている。
であればなおさら、次の世代の役割は、アイデンティティを持つチーズをつくること。
そもそもヨーロッパのチーズだって多種多様。それは、それぞれの風土のなかでできることをしてきた結果としての個性なのだから。
上軍川の牧草地で暮らし、在来種の草と地産の餌を食べて育つ山羊。
彼女たちから分けてもらったミルクに、圭介さんは、加熱殺菌処理を施さない。殺菌は、文字通りチーズづくりに必要な菌まですべて排除してしまうからだ。天然の乳酸菌や酵母を失えば、人為的に培養したそれらを添加しなければならなくなる。
『山田農場チーズ工房』では衛生管理と検査を徹底したうえで、無殺菌乳を選択している。そうして動物のミルクにも、人の肌や建物にも、空気中にも存在する、天然の乳酸菌や酵母の力で発酵させるのだ。
「この環境にいる酵母は、主に3種類。その中でもこいつ(酵母)にがんばってもらおう、など方向づけしていくことはできるんです」
目に見えない微生物の世界で、そんなことができるのか。
驚いていると、圭介さんは「見えなくても、感じることはできるから」と教えてくれた。
「たとえばグラウンドの土と、畑の土。グラウンドの土を手に取っても、ここには生き物が何もいない感じがするけど、畑の土は〝生きてるなぁ〟とわかる。見えないけど微生物を感じますよね?そういう感覚です」
熟成は地下室で、電気エネルギーを極力使わずに、土中の温度や湿度に従って「時」を待つ。この「時」を見計らうのも、ものをつくる人間の仕事である。
「夏のミルクはどうしても脂肪分が低くなるので、少しやわらかめにもっていこうとか。狙った通りになってきて、今すごい楽しいですよ」
夫妻のチーズは「GARO(ガロ)」。アイヌ語で「谷間の岩がゴロゴロしている場所」を意味する、この地の古い呼び名である。
チーズに合わせる、ワインもつくりたい
圭介さんは、興味を持ったらなんでも自分でつくってしまうらしい。
牛や豚を飼って、牛のチーズや豚の生ハムも手がけたこともあったし、10年ほど前からは、農場の一画でワイン用ブドウ品種の栽培を始めている。
幸い、農場は標高200〜300メートル。土壌は火山灰地質で水はけがよく、寒暖差もある、ブドウ栽培に向いている土地だ。何より身近にはワイナリーの『
農楽蔵
』という、頼りになる先生もいてくれる。
「ワインが好きで、自分で育てたブドウのワインと、自分のチーズを合わせてみたいから」
単純ですよ、と言うけれど、試行錯誤と努力を続けて10年だ。
台木(土台となる木)に接ぎ木する一般的な植え方でなく、土へ直に植える難易度の高い手法を採用。そのため成長が遅く、未だ醸造できる収穫量には至っていないというのに諦めず、年々の進歩を喜んでいる。
もう一つ、「ワイン好き」だけじゃない理由があったのだ。
「山でできることは、放牧と果樹なんです。うちの実験が成功すれば、同じように山で酪農をしている人にも、これから農業を目指したい若い人たちにも役立つかもしれません」
山羊たちにブドウの芽や葉、実をバリバリつまみ食いされてしまって、あわてて柵を造ったこともある。考えてみればショックな出来事なのに、山田さん夫妻が語ると楽しそうなのはなぜだろう。
「山羊もブドウが大好きなんですけど、
いたってのんびりペースだが、
ガロの風土から生まれたチーズとワインを、
挑戦も失敗も学びも呑み込んだ、その先に結実する「ものづくり」

- 山田農場チーズ工房
- 標高200〜300メートルの山で、山羊と羊を放牧。
できる限り自然に育て、自然なチーズをつくる。 併設の直売所では、ガロのチーズ、農場のジャム、ホエイ石けん、 調味料、ナチュラルワイン、自然酒などを販売。 - 直売所|北海道亀田郡七飯町上軍川900-1
TEL/FAX|0138-67-2133
営業時間|土・日・祝日10:00-16:00(平日は要予約)
※地方発送あり
※1~3月は冬季休業
NEXT CHAPTER
新連載「僕らの新しいローカリズム」、スタートは北海道・函館編から。
石畳の坂道に洋館が建ち並ぶ港町風情と、雄大な自然が静かに溶け合うこの地に惹かれたつくり手たちを、全9回にわたってお伝えします。
次回は、5月23日ー 毎月、満月の日に新たな記事を更新
CHAPTER 08 『おおば製パン』 comming soon