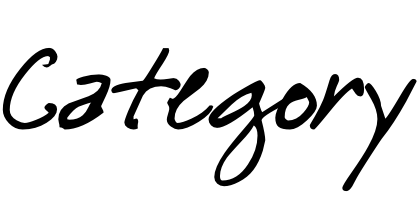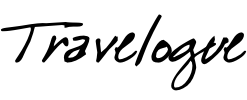 僕らの新しいローカリズム
僕らの新しいローカリズム

僕らの新しいローカリズム|岡山・蒜山
岡山と鳥取の県境にある真庭市蒜山は、山麓に広がる高原地帯。
蒜山高原ではジャージー牛が放牧され、そのミルクでイタリアのチーズが作られる。
津黒高原には、かつて中和村と呼ばれた地域がある。人口600人弱。
観光地でもないこの里山に、しかし近年ではものづくりの移住者が相次いでいる。
農家、豆腐職人、鰻職人、料理家、醸造家、陶芸家、金工作家。
地元の人が「何もない」というこの土地が、彼らを惹きつける理由はなんだろう?
写真/伊藤徹也 文/井川直子
CHAPTER 14 『小屋束豆腐店(こやづかとうふてん)』
白くてやわらかい食べものに救われた
蒜山の山あいを車で走り、真加子トンネルを抜け中和村(ちゅうかそん)地区へ入ると、ほどなく『
小屋束豆腐店
』が見えてくる。
小山を背にしてぽつんと建つ一軒。この地区で唯一の豆腐店を商う豆腐職人は、妻であり、一児の母でもある松井美樹さんだ。
彼女とは、遡ること9年前の2015年秋に会ったことがある。
『
蒜山耕藝(ひるぜんこうげい)
』を訪ねたとき、「もうすぐ移住する豆腐職人がいるんです」と紹介されたのが松井さんだった。
「豆腐職人」というワードも新鮮だったが、現れたのが1985年生まれのニット帽を被った女性、というフレッシュなビジュアルも想定外。彼女は地元の出身でもなく、豆腐店の娘でもないという。
「東京で会社勤めをしていた頃、体調を崩して、食べものを受けつけられない時期があったんです。でも一つだけ、食べたくなったのがお豆腐。白くてやわらかい食べものに、救われました」
しかし日々、会社帰りにスーパーの豆腐コーナーへ寄るうち、なぜか商品に手を伸ばせないことが増えていく。これが食べたい、と心から思える一つが見つからない。棚にはたくさんの銘柄が並んでいるけれど、どれも似ているように思えたのだ。
「もっと多様性があってもいいのにな、と」
地方の豆腐店を訪ね、取り寄せ、東京の個人店を巡る。豆腐のことばかり考えているうちに、業界が抱える問題にも気づいていった。
「お豆腐屋の廃業が、年々増えているという現状です」
1960年には、全国に5万軒を超える豆腐店が存在した。今のコンビニほどの数だ。誰もが鍋やボウルを持参して、近所の贔屓店で作りたてを買った時代である。
それが大量生産化によって、今や専門店の数は10分の1以下。日本人にとってなくてはならない食品だというのに、それを作る店や職人は失われつつあった。
もちろん大量生産の安定、均質、低価格は大事だが、それ一色では土地やつくり手の個性という分野が抜け落ちて、なんだか不健全だ。
「私たち世代が、製法という面でも選択肢を残し、多様性を伝えていけたら」
オンラインショップやSNSが普及した今ならば、作りたい豆腐を小さく作り、小さく売って、暮らしを立てることができるかもしれない。
沸き立つ心のままに、松井さんは会社を辞め、東京・深川新大橋にある明治創業の『
美濃屋(みのや)豆腐店
』で見習いを始めた。
この光景の一部になりたい
独立を考え始めた頃だ。
故郷の鳥取県と隣り合う岡山県に、自然栽培で米や野菜、大豆を育てる夫婦がいると聞いた。屋号は『蒜山耕藝』。彼らはカフェ『
くど
』も営み、畑の作物を使った食事がまたおいしいという。
そこで帰省した際、軽い気持ちで食事に出かけた。
「まず、出されたお水にびっくりしてしまったんです。おいしいというより別格。清らかというか、身体にしみていくというか。それまではどこかの都市部で独立するつもりでしたけど、こういう場所で作るお豆腐にはきっと敵わないと思いました」
どうしてだろう?車でたった1時間の距離なのに、山あいを走り真加子トンネルを抜けた途端、空気が変わる、水が異質になる。
『蒜山耕藝』の高谷裕治さん・絵里香さん夫妻のナチュラルな空気感や、それに惹かれて集まる都市の人、彼らを迎える地元の人が混じり合う、風通しのいい里山の光景。
自分もこの光景の一部になりたい。
そう願ってすぐに、東京から段ボール箱2個で蒜山へ引っ越した。
真庭市では、移住したい人のためのファースト・ステップとして、空き家を利用した「
お試し住宅
」を紹介している。
これを足がかりに基盤を固め、松井さんは2018年、元イノシシ料理店を改装して『小屋束豆腐店』を開業した。
薪の火は山のため、豆腐のため
2024年5月、9年ぶりに再会した彼女は、頼もしい豆腐職人の顔になっていた。
『小屋束豆腐店』の豆腐は、昔ながらの製法である。大豆は、同じ中和村地区で自然栽培されている『
禾(こくもの)
』のサチユタカを中心に、信頼できる生産者たちからまかなう。
「当初は自然栽培にこだわったわけではないけれど、洗うときに“実のしっかりとした綺麗な大豆だな”とか、工程、工程で素晴らしいと思わせてくれる瞬間があるんですよね」
その大豆を、まずは地下水に浸ける。自分で自分の身を守りながら強く育った大豆は、彼女いわく「細胞がぎしっと詰まって」水を吸うにも時間がかかる。暖かい時季なら丸1日と少し、冷え込む時季は前々日から浸け、人間はただ彼らのペースをゆっくりと待つしかない。
「でも、浸け過ぎもよくありません。“豆が溺れる”といって、立つべき泡が立たないとか、固まりにくいなど後々まで影響します」
パンパンに膨らんだ大豆をすり潰し、水を加えたものを生呉(なまご)という。これを炊く地釜は、左官職人に造ってもらったもの。修業先ではガス火だったが、ここでは薪火だ。
加工場の周りにはナラ、クヌギなど薪材に向く広葉樹が多いからである。プロパンガスを運ぶより経済的なうえ、薪は山のためにも、豆腐のためにもなってくれる。
「木を燃やすエネルギーの“陽”の強さは、東洋医学的に“陰”の食材といわれるお豆腐と相性がいい。味が立体的になり、大豆の味が立ちます」
決してあたりまえのことじゃない
生豆の青っぽい香りがナッツのように変化する頃、むくむくと泡が立ち、やがてカプチーノのようなムース状に変わった。
泡の正体は、大豆に含まれるサポニンという成分。昔は米ぬかを少量加えて泡を抑えつつ、それでも止まない泡を、煮物のアクを取るように根気よくすくったそうだ。
この手間と時間を解消すべく、現代では消泡剤を使うのが一般的なのだが、彼女は泡と戦うのではなく共存を選ぶ。
「消泡剤が悪いとは思いませんが、泡が悪いとも考えません。濃密な泡が蓋となって、その下にある呉を育ててくれる。私にとっては味方です。この泡がキラキラしてきたら、『蒜山耕藝』の米ぬかをほんのちょっとだけ上から散らすんです」
つきっきりで混ぜながら炊くこと、2時間半あまり。火の通った煮呉を搾っておからと豆乳に分けたら、いよいよ「にがり寄せ」と呼ばれる工程がやってくる。
豆乳の温度が頃合いになったら、にがり(室戸の海洋深層水にがり)を数回に分けて混ぜながら加え、ほどよい固まり具合に仕上げていく。職人のセンスと見極めが試される、正念場だ。
「ここでバチッと決めることで、味の持ちが違う、日が経ってもおいしいお豆腐になります」
鍋の中でふるふるになったところを、すくい上げれば寄せ豆腐、木型に注いで水分を抜き固めると木綿豆腐だ。
アナログな製法、製造はワンオペ、4歳児(当時)の子育て中。どれも自分で選んできた道である。豆腐作りは週1〜2回、油揚げは2日がかりで週1回のスローペースだけれど、『くど』をはじめ県内外の飲食店、イベント、オンライン注文は絶えない。
「私が恵まれているのは、土地の大豆を、同じ土地の水と山の木でお豆腐にできるということ。それは自分ひとりではできないし、決してあたりまえのことじゃない」
夜明けの加工場で、黙々と豆腐に向き合う時間。水の流れる音、薪がパチパチと爆(は)ぜる音、地釜の中で炊かれる呉の音。
それらを慈しみながら作る彼女の豆腐は、大豆のふっくらとした香りにも、芯の通った味わいにも外連味(けれんみ)がない。すとんと、心が在るべき場所に落ち着くような感覚を覚えるのだ。

- 小屋束豆腐
- 地釜と薪火による「小屋束豆腐」は、オンラインから購入可。最も水分を含む「一」と濃厚さ(固さ)を増した「三」の寄せ豆腐、「五」の木綿豆腐を定番として販売。おからはグラノーラにアップサイクル。6〜9月は、月に1回直売も行っている。屋号の「小屋束」とは、屋根を支える建材の名称。「家族の日常を支える食であるように」の願いを込めた。
NEXT CHAPTER
「僕らの新しいローカリズム」岡山・蒜山編は、全6回でお届けいたします。
次回は、12月15日ー 毎月、満月の日に新たな記事を更新
「時間がおいしくしてくれるもの」をテーマに岡山・蒜山の森と東京を行ったりきたりしている料理家『オカズデザイン』の家を訪ねます。
CHAPTER 15 coming soon