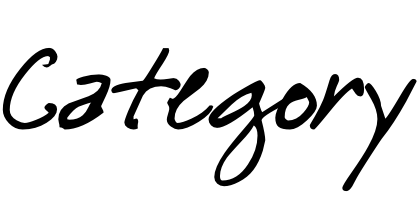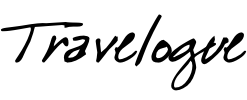 僕らの新しいローカリズム
僕らの新しいローカリズム

僕らの新しいローカリズム|岡山・蒜山
岡山と鳥取の県境にある真庭市蒜山は、山麓に広がる高原地帯。
蒜山高原ではジャージー牛が放牧され、そのミルクでイタリアのチーズが作られる。
津黒高原には、かつて中和村と呼ばれた地域がある。人口600人弱。
観光地でもないこの里山に、しかし近年ではものづくりの移住者が相次いでいる。
農家、豆腐職人、鰻職人、料理家、醸造家、陶芸家、金工作家。
地元の人が「何もない」というこの土地が、彼らを惹きつける理由はなんだろう?
写真/伊藤徹也 文/井川直子
CHAPTER 15
『オカズデザイン』
荒れた森を再び生かしてくれるなら
『オカズデザイン』
の名前とその料理は、映画、書籍、広告など多くの媒体で目にすることができる。グラフィックやプロダクトのデザイナーでもある吉岡秀治さん・知子さん夫妻による、料理とデザインのチームだ。
彼らのテーマは「時間がおいしくしてくれるもの」。
時間にしかつくれない味がある。その真意は、煮込み時間や発酵期間のことだけではなくて、季節の巡り、種を蒔くことから始まる実りといった時間軸の話である。
風土、水、空気、人。
食を大きなスケールで俯瞰する彼らは、2018年から東京と岡山・蒜山(ひるぜん)との2拠点生活を始めている。
「水が圧倒的によかったんです」
北陸や四国、九州まで土地を探したという二人に、なぜ蒜山?と訊ねたら、そう返ってきた。
やわらかで澄み切った味わいの水。ただ飲んでも身体に染み込むようだが、その浸透力、親和性の高さはだしを取るといっそう感じる。素材の細胞間へするりと入り込み、持ち味を引き上げてしまう不思議な水だ。
2024年5月、蒜山のご自宅へ伺った。
中和村(ちゅうかそん)地区の中でも、集落を離れ、県道からも逸れた最奥地。湧き水の川筋にあたる土地で、上流には民家がないため生活汚染の心配もない。
というか、小川も含む7千坪の山林にぽつんと家が建っている。前の持ち主から「荒れた森を再び生かしてくれるなら」という条件で託されたのだった。
待ってるんですよ、森が
里山の森は、人間が適切な手を入れることで健全に保たれていく。
少しずつ草を刈り、間伐や植樹を施して再生中の裏山は、名づけて「オカズの森」。
秀治さんは蒜山の家へ着くと、休む間もなくカゴを担いで森へ「すっ飛んで」行く。
「待ってるんですよ、森が」
春には山菜が待っている。こごみ、たらの芽、少し遅れてミズ、わらび。里と森の境界には蕗(ふき)が群生し、標高600メートルを超えると根曲がり竹が採れる。
初夏には木苺や、味が濃く香りよい熊苺を収穫し、ヴィネガー作り。黒文字の枝葉は、ラムやウォッカに漬けてお菓子に使う。
夏から秋にかけては木の実とキノコの天国だ。ジュニパーベリーに似たカヤの実、栗、胡桃。フンギ・ポルチーニの仲間といわれるヤマドリタケや、マツタケも見つかる。
冬は冬でムキタケやキクラゲが現れ、雪が降るとエノキダケがおいしくなる。
こんな四季折々の食材が、「うちの裏」で採れる豊かさ。
この日は取材班のために、二人が探し出したわらびやハチクで、知子さんが山菜丼を作ってくれた。
『パパラギ農園』
の平飼い鶏の卵でとじて、森の入口に植えた山椒の葉を仕上げにパラリ。
「ちょうど花が咲き終わって、実山椒にはまだ早くて」
それでも山椒の葉は、1年を通して活躍してくれる。
東京−岡山は、車で片道10時間。
車でなければならないのは、蒜山の湧き水や食材を、彼らが営む
『カモシカ』
で振る舞うためだ。
「そのための2拠点です。完全に移住して、蒜山の恵みを自分たちだけで享受するのでなく、東京の人に味わってもらうのが私たちの役割なんじゃないかと」
蒜山でインプットし、東京でアウトプットする。それが彼ら自身の「呼吸」になっているのだと二人は言った。
山の水を、お風呂で浴びた気持ちよさ
『カモシカ』は、シンプルで美しく、長く使い込むことで風合いが増していく器や生活道具と、『オカズデザイン』による料理の店だ。
ここで度々展示を行ってきた陶芸家の
堀 仁憲(かずのり)
さん、金工作家の
さかのゆき
さん夫妻もまた、吉岡さん夫妻と同時期に蒜山と出合い、家を建てて2019年から暮らしている。
彼らは蒜山へくる前に一度、東京から岡山県内の吉備中央町に移住したことがある。東日本大震災がきっかけだった。
堀さんは「自然のなかで、畑を耕しながら陶芸の仕事ができる暮らし」を求め、さかのさんは「水」の大切さを痛感。どちらも叶う土地を探したのだが、吉備中央町の家は井戸が浅く、水がすぐに止まってしまう。
どうしたものか。考えていた矢先に、
『蒜山耕藝(ひるぜんこうげい)』
の高谷裕治さん、絵里香さん夫妻と知り合った。
「遊びに行ってみようか、ってオカズさんたちと蒜山を訪れたんです。すると車を降りた途端、空気が違った。なんだここは、と。でもそれ以上に、私が絶対に住むと決めたのは高谷さんの家のお風呂を借りたとき。飲んでもおいしい山の水を、全身に浴びたときの気持ちよさ!このお風呂に一生入りたいと思いました」
地元の人たちと信頼を築いて得られた土地は、折り重なる小高い山々の懐に抱かれるような、美しい沢のほとりだった。さかのさんは「あまりにも神々しくて、人が住んじゃいけない」と感じたほどだ。
「僕は違って、ここしかないと。この風景の中に家がある、そのイメージができたんです」
自然に溶け込む平屋の母屋と離れは、堀さんが、大工や左官職人らとともにゼロから造った。
石場建てと呼ばれる伝統構法(基石の上に柱を置き、金具などを使うことなく組木や構造によって安定させる)の駆体はさすがにプロに任せたが、壁塗りは職人とともに行い、内装はほぼ一人で仕上げた。
さかのさんのアトリエは母屋の中にあり、台所とも行き来して、好きな料理やお菓子づくりも楽しめる。
堀さんの工房は離れのほう。二人一緒のお茶の時間がくると、彼は創作の手をいったん止めて、外の空気を吸いながら母屋へと向かう。
悠々とした時間の流れ、山の静けさの中で営む、ものづくりの仕事と暮らし。
水は120メートルの深さから汲み上げる井戸水だ。飲み水はもちろん、顔を洗ったり洗濯したりする水でさえ、山へ80年前に降った雨が土中を旅して辿り着いた伏流水である。
蒜山の空気を『カモシカ』でお裾分け
都市で生きる私たちもまた、蒜山と無縁ではない。
この土地から生まれる味と作品に、東京の『カモシカ』で出合うことができるのだから。
蒜山の取材から帰ってすぐの5月末、『カモシカ』で堀さんの個展が開催された。
蒜山の工房で土と向き合っていた、堀さんの器。光と影の美しいアトリエで、さかのさんが鍛錬していたカトラリー。
吉岡さん夫妻が森へ分け入って採ってきた山菜。『蒜山耕藝』の田畑の実りと、
『小屋束豆腐店』
の地釜と薪火で作る豆腐やおから。
それらが一同に会し、同じテーブルに載る。
真夏日の太陽が照りつけるなか辿り着くと、オカズの森で聞こえた小鳥の声が迎えてくれた。
料理は、天然クレソンのポタージュからスタート。なめらかな白い碗に、はっとするほど深いグリーン。堀・さかの家の沢に自生していた、あのクレソンだ。
洋白という、どこか温かみを感じる金属のスッカラで口に運べば、とろみのある液体がすいっと流れ込む。
「クレソンってこんな味だったんだ」
参加者のひとりが呟いた。たしかに、クレソンに旨味があったとは。加熱してあるのにみずみずしく、苦みもエグみもない。
オカズの森で早採りした、繊細な風味のわらびは鯵とたたいて。
『蒜山耕藝』の鳴門金時は、秋に収穫してひと冬熟成させ、甘味を極めたフライドポテトに。
「一年で最も味がのる」時季のきゅうりは、フレッシュなコリアンダーと『小屋束豆腐店』のおから和えに。
大豆とビーツの軽やかなフムス、大根のさや(花が終わり、種になる前の実)のさわやかなピクルス。シェパーズパイの具は、蒜山産イノシシの優しいラグー。
真打ちは、『蒜山耕藝』のごはんである。
土鍋で炊いたササニシキはグミのような弾力を持ち、噛めば旨味が滲む。
そこへ、かき揚げだ。名残のそら豆、赤新玉ねぎ、帆立貝のひもをバリッと音が立つくらいからりと揚げ、ごはんの上にのせたところへ、堀さん作のティーポットからお茶を注ぐ。ふわっと山椒の風味が香る緑茶は、蒜山の湧き水で出したものだ。
色とりどりの味わいと食感が、口の中で花火のように弾け、一緒に溶けた。
食べ終えた参加者が、みな安寧に満ちた顔をしている。また小鳥が鳴いて、オカズの森でそうしたように、少しゆっくり呼吸してみた。
「東京の人にこそ、蒜山の空気が必要」
ああそうか。吉岡さん夫妻が届けたかったのは、こういうこと、だったのだ。

- オカズデザイン
- 料理とデザインのチーム。器と料理の店『カモシカ』で扱う作品は、シンプルで美しく、使い込むと風合いが増していく器や衣服、道具など。展示期間のみオープンし、食事会では作家の器や道具を実際に使って料理を味わえる。
NEXT CHAPTER
「僕らの新しいローカリズム」は、新たな地、
北海道の大雪山連峰・旭岳の麓に位置する『美瑛(びえい)・東川』。
2017年からこの地に移住をされオープンした『Vraie(ヴレ)』というレストラン。
旅や人との出会いから育まれるひと皿をつくりだす、村上智章シェフを訪ねます。
次回は2025年1月14日―毎月、満月の日に新たな記事を更新。
coming soon