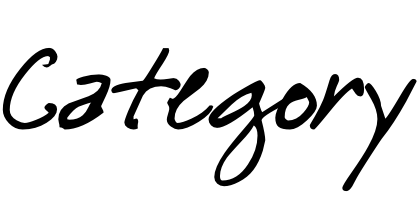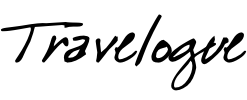 僕らの新しいローカリズム
僕らの新しいローカリズム

僕らの新しいローカリズム|岡山・蒜山
岡山と鳥取の県境にある真庭市蒜山は、山麓に広がる高原地帯。
蒜山高原ではジャージー牛が放牧され、そのミルクでイタリアのチーズが作られる。
津黒高原には、かつて中和村と呼ばれた地域がある。人口600人弱。
観光地でもないこの里山に、しかし近年ではものづくりの移住者が相次いでいる。
農家、豆腐職人、鰻職人、料理家、醸造家、陶芸家、金工作家。
地元の人が「何もない」というこの土地が、彼らを惹きつける理由はなんだろう?
写真/伊藤徹也 文/井川直子
CHAPTER 13 『蒜山耕藝(ひるぜんこうげい)』
米のすべてが飲める酒、どぶろく
「代満」と書いて、「しろみて」と読むのだそうだ。
代(しろ)とは田のこと。「満てる」は中国地方の方言で、使い切る、無くなるという意味。
米づくりは、冬を越えて固くなった田へ水を引き、土を搔きほぐして再びやわらかな田に戻す作業から始まる。これを代掻き(しろかき)といい、代掻きをして苗を植え、植えるべき苗がなくなったら代満て。
つまり「代満」は、今年の田植えが無事に終了したことを指すと同時に、それを田の神に報告して、神と人間とがともに祝う行事のことでもある。
歓びと感謝と、米づくりの始まりとが溶け合う、なんと多幸感あふれる言葉だろう。
『
蒜山耕藝(ひるぜんこうげい)
』の高谷裕治さんが2023年から醸造するどぶろくには、この「代満」が名付けられている。
「田の神様と飲むなら、米が育った田と同じ土地の水で醸されたお酒がふさわしいと思いました。“しろ”という響きも、白いお酒であるどぶろくにつながります」
米、水、米麹を発酵させて、醪(もろみ)を造るところまでは日本酒と同じ。だが醪を搾って酒粕を取り除く日本酒に対し、どぶろくは搾らず、発酵した固体混じりの液体がまるごと酒になる。
だから日本酒は基本的にクリアで(にごり酒でも搾りの工程は入る)、どぶろくは米の白い色そのままだ。
自然栽培で米を育てるように、酒を醸す
米は島根県安来(やすぎ)で150年ほど前に生まれたうるち米、「亀治(かめじ)」。無肥料でも育つよう一人の農家によって開発されたが、化学肥料の普及とともに忘れ去られ、1995年に志ある農家が復活に尽力した。再び巡りくる自然栽培の時代を、待っていたかのような品種である。
この米を、高谷さんはできる限り削らない。
日本酒ならば大吟醸では50%以上も磨く(削る)ところ、「代満」はごはんと同じ10%。蒜山の天然水を吸わせるにも、硬さのある「亀治」の場合は一晩かける。
米と環境に無理をさせない酒造り。農家である彼は、自然栽培で米を育てるように、酒を醸す。
「代満 どぶろく 生酛(きもと)」。まさに、亀治という米を飲むかのような酒だ。「生酛」とは、既製の乳酸や酵母を使わず、空気中の野生酵母の力で発酵させる醸造法。
私が飲んだ第3号は瓶詰め後も発酵を続け、栓を回すと元気な泡が湧き上がってきた。ぐい呑みにとろりと流れる液体は、三分粥くらいだろうか。溶けかかったやわらかな米粒を口の中で潰しながら味わうと、米の旨味がしっかりと舌にのり、後味はすぱんっと切れた。
たとえば「華やかな香りを」とか「より深い旨味を」とか、高谷さんに、目指す味わいはきっとない。
むしろ造り手の思惑を乗っけずに、米と水と麹菌がどう発酵していくか。醸されたどぶろくの無垢なのびやかさは、蒜山で目にした田んぼ、小川、集落、森の、過剰のない生き様(よう)と重なった。
『蒜山耕藝』という世界観
『蒜山耕藝』は、岡山県真庭市蒜山で自然栽培の農業を営む、高谷さんと妻の絵里香さんの屋号である。肥料も農薬も使わずに稲作ができる土地を求めて、二人は関東から2011年に、蒜山の旧中和村(きゅうちゅうかそん)地区へ移住した。
標高450メートルの高原地帯にあり、川の源流に近く、水の綺麗な里山だ。
「山に囲まれた人里ですから、人間が何もしなければ山は荒れていくし、適切に手を入れてやれば生き生きとする。人と自然がともに生きている感覚があります」
裕治さんがそう言うと、絵里香さんは「13年住んでもなお、毎日綺麗な風景だなぁと思う」と答える。
彼らは米・小麦・豆などの穀物と野菜を育て、自分たちの糧とするだけでなく、さまざまな食品や調味料といったプロダクトをつくっている。
そのラインナップが、ちょっとニッチでチャーミングなのだ。
醤油、味噌、麹といった基本の調味料のほか、きなこに餅、パスタ、もなかの皮に白玉粉。今、家でこういう昭和っぽいおやつを作る人は少ないんじゃない?なんて心配は余計なお世話で、いつも『蒜山耕藝』のオンラインショップに登場するやいなや完売だ。
絵里香さんいわく、どれも「自分たちが食べたいもの」。
だから白玉粉や餅になるもち米が、滋賀羽二重糯(しがはぶたえもち)という高級和菓子に使われる品種だったり。
食べたい作物を育て、食べたいものをつくる。といっても彼らの仕事は田畑の上で、そこから先の加工は老舗の工場(こうば)や職人、ロゴやパッケージはデザイナー。各分野のプロと手を結ぶことで、地域の技術、伝統、産業を結びつけることができるから。
高谷さん夫妻は、蒜山の田んぼから社会を見ている。私たちは、ほっとする味わいの味噌や香ばしい黄粉を通して、いつの間にか『蒜山耕藝』という世界観に共鳴している。
旧中和村にいくつかある集落の一角に、夫妻が営むカフェ『くど』がある。この地域で「台所」を意味する名前だ。
地元の左官職人に手ほどきを受けながら、ほぼDIYで改装した建物。古い蔵を解体した土を再利用し、稲藁を混ぜて壁に塗る。乾燥して自然に貫入した土壁に、古道具の照明があたたかく灯り、真ん中には木工作家による大きなテーブル。元はボロボロの資材置き場が、誰もが「素敵」と溜め息をこぼす空間に生まれ変わった。
訪れるのは、多くがよその人たちだ。オンラインで『蒜山耕藝』の世界観に惹かれた彼らが、リアル蒜山の水のやわらかさや、作物を使った料理や菓子のしみじみとした味わいを体感する場所。
迎える絵里香さんは鎌倉のカフェ「ヴィヴモン・ディモンシュ」出身、いわばカフェのプロである。
2014年12月にオープンした『くど』には、ものづくりに携わる人々が多く集まり始めた。
豆腐職人、料理家、蕎麦職人、パン職人、彼らの食を盛る器の陶芸家にカトラリーをつくる金工作家。『
蒜山鰻専門店 翏
』の鰻職人・村田翏さん、朋子さん夫妻や、『
蒜山醸造所 つちとみず
』のクラフトビール醸造家・杉保志さん。
そうして個性的なつくり手たちは、続々と蒜山への移住を決めてしまったのだ。
今、『くど』は、そういった作家や伝統工芸の展示会、料理会、音楽に絵画など、さまざまな企画展やイベントも行う蒜山のカルチャー基地になっている。
『蒜山耕藝』は、この里山に小さな「種」を蒔いた。
「人がよく生きるということ」を考え続ける二人が、同じく求め続ける人々の心を動かし、つながっていく。軽やかに、爽やかに。
「自然栽培と同じです。無肥料でも、田畑には必要な要素がいつの間にか集まってきて、育つ作物は元気に育つ」
蒜山は今、ユニークな微生物が集まって生態系を育もうとしている土壌なのだ。

- 蒜山耕藝
- 米を中心に、穀物、野菜を自然栽培で育てる。これらの作物から生まれる調味料や菓子はオンラインで販売。カフェ『くど』は、農作業を優先させながらの不定期営業(最新情報はインスタグラム 参照)。
NEXT CHAPTER
「僕らの新しいローカリズム」岡山・蒜山編は、全6回でお届けいたします。
次回は、11月16日ー 毎月、満月の日に新たな記事を更新
岡山県蒜山の山あいで薪の火と、源流域の清らかな水の力を借りて、豆腐作りをされている『
小屋束豆腐店
』を訪ねます。CHAPTER 14 coming soon