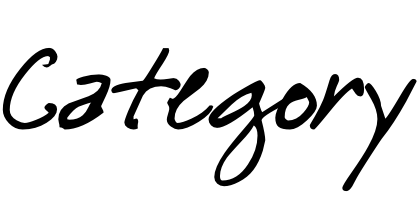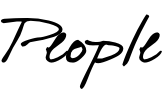 想いをつなげる
想いをつなげる

300年以上の歴史を持つ、和歌山・御坊の醤油蔵『堀河屋野村』。
数年前、17代目・野村太兵衛さんが語った「本物しかつくらない」という哲学に触れました。
そして今回、改めて蔵を訪ね、18代目 野村圭佑(太兵衛襲名予定)さんにお話を伺いました。変わらず木桶で仕込まれる醤油には、伝統とともに、未来へ向かう新しい物語が紡がれています。
「三ツ星醤油」ができるまで

- 醤油の原材料の大豆、小麦、塩
醤油は、大豆・小麦・塩の三つの材料からつくられます。堀河屋野村では一本の醤油が完成するまでに、いくつもの手しごとと時間が重ねられています。
まずは小麦の焙煎。「ほうろく」と呼ばれる大きな鉄鍋を薪の火で温め、焦げないように竹箒でかき混ぜながら丁寧に炒っていきます。醤油の香りは、この香ばしい小麦から生まれます。
次に大豆の炊き上げ。「三州釜」と呼ばれる大きな鉄の窯に大豆を入れ、水に浸してから釜の火でじっくりと炊き上げていきます。紀州は材木が豊かで、その日の天候や大豆の状態に応じて薪を使い分けているといいます。少しずつ薪をくべ、煮上がったら薪入れをやめ、火種が小さくなるのを待ち、最後は余熱で蒸して完成。こうして大豆はふっくらと炊き上がり、大豆本来のおいしさが引き出されるのです。
ここから炒った小麦と炊き上げた大豆に麹の原菌を加え、麹づくりが始まります。堀河屋では「手麹」と呼ばれる江戸時代からの製法を守り、温度と水分の塩梅を見極めながら進めます。最適な温度を保つために、秋や春はゆったりと、冬は温度を逃さぬよう迅速に。自然の条件に人が合わせる、柔軟さが大切だと野村さんは語ります。
麹のもとができたら、専用の麹室(こうじむろ)で4日間寝かせます。堀河屋野村の麹室は江戸時代から続く建物で、有形文化財にも指定されている独特のつくり。天井が低いのは、当時の人々の身長に合わせた名残です。
最大の特徴は窓があること。通常の麹室は密閉され外気を遮断しますが、ここでは逆に蒸気を逃すために窓を開けることがあります。過度な湿気は、麹の生育に邪魔をしてしまいます。雨の多い和歌山では工夫も欠かせません。大雨の日には薪の量を増やしたり、大豆を硬めに炊くことで、余分な湿気があっても麹がべたつかないように調整します。こうした知恵と工夫こそ、300年続く堀河屋独自の製法なのです。
麹室で4日間かけてできた麹は木桶が並ぶ「仕込み蔵」に運ばれ、桶に塩水と交互に入れられていきます。一度の仕込みで1桶が満たされるわけではなく、週に数回の仕込みを積み重ね、約3週間分でようやく1桶ができあがります。年間で70回ほどの仕込みを行い、10桶前後が並ぶことになります。
桶の中では、仕込んだ時期によって環境が異なるため、発酵の進み具合にも個性が生まれます。まるで4月生まれと12月生まれの子どもが成長速度に違うように、麹もそれぞれの歩み方を見せるのです。
「普通だったら順番に発酵が進むはずなんですけど、稀に12月生まれが先に育つこともある。まさに子どもと同じで、予想外の成長を見せるんです。だから面白いですよね」と野村さんは語ります。 塩水に浮かんでいた麹は、「櫂入れ」と呼ばれる撹拌を繰り 返すことで次第に発酵が促進され、 やがて赤茶色の濃厚な「諸味」へと姿を変えていきます。木桶の中で1年半から2年。紀州の温暖な気候が発酵条件に適しているのです。野村さんは諸味の様子を子どもを見守るように確かめながら、その育ち方に寄り添っていくのです。
ふた夏かけて育った諸味は布袋に入れられ、積み重ねてゆっくりと圧力をかけることで搾られます。にじみ出た液体こそが、醤油のもととなる「生揚げ醤油」です。
最後の仕上げは火入れ。最初に大豆を炊いたのと同じ大釜で、4時間かけてじっくりと加熱していきます。火入れをするのは、醤油の中に残る酵母菌の活動を止め、品質を安定させるため。生のままでは菌が生き続け、光や温度変化によって表面に膜を張り、香りや味を損なってしまうのです。
火入れによって発酵が静かに落ち着き、香ばしい香りが立ち上がります。こうして旨みを壊さずに仕上げられた醤油は、ようやく一人前の味わいを備えた「三ツ星醤油」となるのです。
自分にしかできないこと
現当主の圭佑さんは、大学卒業後に東京の総合商社へ入社し、大豆の輸入を担当していました。扱っていたのは主に搾りかすで、鶏や豚、牛の飼料として国内外の飼料メーカーに販売する仕事。インドやブラジル、アメリカ、中国から大量に大豆を仕入れ、先物市場や海上運賃まで管理する日々は、ダイナミックで刺激にあふれていたといいます。
そんななかで気づいたのは、大豆が「食べ物」ではなく「油を搾る種子」として世界では認識されているという事実でした。日本では当たり前に豆腐や味噌、納豆、醤油として口にしてきた大豆が、世界では「オイルシード」と呼ばれ、油の原料として扱われている。 「そのとき、日本の大豆ってどうなっているんだろう?と考えるようになったんです」と振り返ります。
そこで、世界の大豆を扱う経験と、実家が大豆を原料とする醤油屋であることが結びつきます。「これだけ大豆を知ってから醤油や味噌をつくることは、他の人にはできないミッションだと思ったんです。国内の大豆がどう育てられ、大豆食の文化がどう続いてきたかを、醤油や味噌づくりを通じて伝えていくことには社会的な意義がある、そう考えるようになりました。」
商社での仕事は楽しくやりがいのあるものでしたが、圭佑さんの心は次第に家業へ向かっていきます。2011年、『堀河屋野村』に戻り、醤油屋としての人生を歩み、今に至ります。
食卓に置く一本を選ぶ
堀河屋野村の醤油づくりは、すべて手作業で手間ひまを惜しまず続けられてきました。大豆を丸ごと使い、木桶で仕込み、自然の流れに寄り添いながらじっくりと育てていく。三百年変わらない方法で、一本の醤油が生まれます。
いま日本で流通する醤油の多くは「脱脂加工大豆」を原料としています。油を搾った後の大豆かすを活用したもので、戦後の食糧難や技術革新の中から広がっていきました。一方で、堀河屋野村は今も変わらず丸ごとの大豆を使い、昔ながらの製法を守り続けています。原料や製法の違いは、そのまま味わいと香りの違いとしてあらわれます。
日本人にとって醤油はとても身近な存在です。それほど欠かせない調味料だからこそ、違いを知って選ぶことに意味がある。食卓に置く一本をどう選ぶかで、日々の味わいは変わっていきます。そして、その選択は、次の世代の食卓にもつながっていきます。
自然と人の手で育まれてきた時間を重ねながら、堀河屋野村の醤油づくりは、これからも変わらぬ味わいとともに未来へと受け継がれていきます。
堀河屋野村の味わいをご自宅で
-
- 三ツ星醤油
-
蔵元が大事にしてきた、本物のかおり堀河屋野村の「三ツ星醤油」は、コクがあるけれど濃すぎない、そしてとにかく香りの良い逸品。料理の味を引き立ててくれる、食卓の常備品です。
-
- 徑山寺味噌
-
300年以上に渡り受け継いだ伝統製法「手麹」でつくられた新鮮な地元産夏野菜がごろごろ入った「おかず味噌」。米、大豆の麹の甘さ、瑞々しい夏野菜のフレッシュ感をおたのしみ頂けます。























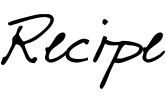 つくるたのしみ
つくるたのしみ