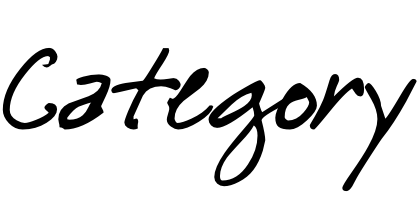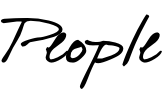 想いをつなげる
想いをつなげる

深みと旨味と愛情と。 しあわせを運ぶ『飯尾醸造』
その一本があるだけで、味わい豊かな食卓へと早変わりーー。そう言われて、名高い酢があります。それは明治26年創業の『飯尾醸造』が大切につくり続けている「富士酢」。昔ながらの製法と、手間と時間をかけたつくり手の愛情がたっぷり注がれています。
きれいな黄金色をした富士酢を舌の上に乗せると、とてもまろやか。これが、本物の酢の味わい。「ツンとしてなくて、旨味があるでしょう」と、にこやかに応じる5代目見習いの飯尾彰浩さんと、その妹である広報担当の淳子さん。飯尾醸造は、京都・丹後の地で、4代目である父・毅さんを柱に、一家4人で日本一の酢を志しています。
酢づくりは、まず米づくりから。その米で麹づくり、酒母づくり、そして酒(酢もともろみ)の仕込みをし、発酵・熟成を経て出来あがります。1本が誕生するまでにかかる月日は、実に2年半。 多くの人に長年愛される秘訣を、彰浩さんはこう語ります。「原材料に、良質の素材をたっぷり使うこと。そして、丁寧な製法を守ることです」。
そのこだわりの一つが無農薬米。“オーガニック”という言葉が浸透する、はるか以前の昭和30年代。3代目である輝之助さんは、地元の上質な無農薬米を求めた結果、周囲の田んぼで散布される農薬や生活排水の影響を受けることのない、山間部の棚田に辿り着いたそうです。棚田には機械が入ることができないため、手間はかかりますが、今も変わらず棚田での米栽培が行われています。そうしてすくすく育った新米を、たっぷり使うのです。その量、1ℓ中200g。これは「米酢」と名乗るためにJASが規定した分量の5倍にもあたります。「だから味に深みがあるんです」と淳子さんが言うように、富士酢には、米の旨味がぎゅっとつまっています。
そして、大切な酒づくり。杜氏(日本酒の醸造を行う際の責任者)と彰浩さんらは、冬の3ヶ月間、自社の酒蔵に泊まり込み、日本酒を完成させます。大吟醸では米の50%を削り精米するところを、18%しか削りません。つまり、旨味成分の多い天然のアミノ酸を含んだ濃醇旨口。これが、酢のためだけにつくられた、贅沢なお酒の正体です。
こうしたこだわりから生まれた原材料を、ふんだんに使い造られる富士酢は、看板商品として全国各地で親しまれています。
一方で、伝統だけでなく、新しいチャレンジも忘れません。「何度もマイナーチェンジをしています。果実酢などの新しいよいものをつくることも含め、より上を目指すことが大切です」と彰浩さん。それもひとえに、人によろこんでもらいたいから。そして、毎日の食卓を支えるかけがえのない存在となるため。誇り高きその一滴がもたらす、味わい深さ。彼らの酢づくりの伝統と挑戦は、これからも続いていきます。
よい酢づくりはよい醪づくりから、よい醪づくりはよい米づくりから”。人里離れた山奥に広がる棚田で、無農薬米を毎年丁寧につくっています。そのお米を使い、自社の蔵で杜氏が醪を仕込み、その醪からお酢を造るのです。110年前の創業から、ほとんど変わらない製法です。






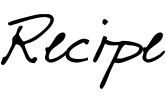 つくるたのしみ
つくるたのしみ