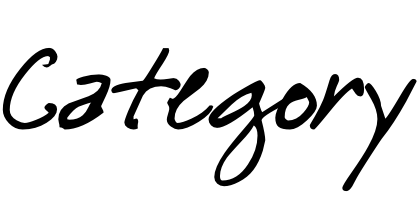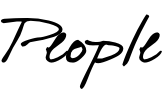 想いをつなげる
想いをつなげる

土地の恵みを生かした、その土地にしかないおいしさを、これからもよろこぶために。最後まで全ておいしくいただくことは大切です。これは、自然物や人がつくるものなどの「もの」に対しても同じ。大切につくられた行く末のしあわせなものは、使うよろこびも増し、一層愛着もわくことでしょう。
そんなものづくりと向き合うつくり手との出会いがありました。北海道の天然染めプロジェクト『BetulaN(ベチュラン)』を主宰する、染色職人・野口 繁太郎さんです。
札幌にある工房を訪ね、お話しを伺いました。
Interview
BetulaN 染色職人・野口 繁太郎さん

- BetulaN 染色職人・野口 繁太郎さん
学名で「白樺」を意味する「Betula」に、『野口染舗』の「N」を組み合わせた『BetulaN』のルーツには、1948年創業の『野口染舗』があります。『野口染舗』は北海道札幌の悉皆屋(しっかいや)として、染み抜きや染め替えなど、着物のお直しの相談を受けてきました。
野口 繁太郎さんは、その5代目。2006年に家業に
「一つは、“最後まで余すことなく大切に使い切る”こと。
私が携わる着物は、洋服と全くちがいます。洋服はパターンをつくって生地をカットし、縫製するので、余分な捨てる生地がいっぱい出ます。着物は直線断ちで、余った生地は中に入れ込み仕立てるので、捨てる生地がありません。家業に携わる前はそれを知らず、初めての染め直しで目の当たりにしたときは衝撃を受けました。
しかも着物は、『最後は雑巾になるまで使用する』と言われるほど。一度仕立てたら終わりではなく、仕立て、ほどき、洗って、染め替えをして、というサイクルが当たり前にあります。着物が教えてくれたことは、譲れない私のベースです。
もう一つが“ローカル”。地元の、北海道という土地でしかつくれないものをつくるということです。
そういう意味でいうと、実は北海道は、着物の産地ではありません。だけど私は、北海道で生まれ、着物に携わっています。家業で積み重ねてきた経験と技術を生かして、ここでしかできないことをと、2023年に北海道の天然染めプロジェクト『BetulaN』を始めました」

- 野口さんの考えの根底には、日本古来の文化「着物」の素晴らしさを未来につなぎたいという思いがある
野口さんが天然染めを選んだきっかけは、2020年に遡ります。
当時、新型コロナウィルスの流行で着物を着る機会が減り、なにか新しいことに取り組まねばと野口さんは模索していました。ちょうどそのとき、地元の集まりでバリスタと出会い、「毎日、大量の抽出後のコーヒー粉を捨てている」という話を聞きます。
「聞いた瞬間、これだ!と。札幌はカフェが多い地域だから、抽出後のコーヒー粉を使って染めれば、“ローカル”なものづくりができます。しかも、本来なら捨てられてしまうものを“最後まで余すことなく大切に使い切る”こともできる。その週にはお店に抽出後のコーヒー粉を譲ってもらいに行き、コーヒーを使った天然染めを始めました」
天然染めは、着物の染め直しとはまた違う難しさがあると野口さんは言います。しかし、天然染めの経験は2020年以前からあったため、コツを掴むには時間がかからなかった、とも。
「天然染料に興味があって、研究していたことがあるんです。そのときのノウハウがあったので、コーヒー染めは1ヶ月ほどでつくり上げることができました。染め方はもちろん、カビないように抽出後のコーヒーの粉を保管したり乾燥させたりする方法にも、当時の経験が生きています」

- 北海道では市の木でもある「白樺」も、ある時ふと“ローカル”な存在だと気がついた
抽出後のコーヒー粉のほかに、『BetulaN』が使うのは間伐された白樺とワイナリーから出たワインづくりの過程で残った果皮。いずれも地元・北海道の、本来なら捨てられるものですが、丁寧に色を抽出して手染めすることで、ふたたび命を吹き込んでいます。
「私が使う材料は、全て顔が見える生産者がいます。白樺なら、山を管理する人たち。コーヒーなら、豆から焙煎するカフェの人たち。ワイナリーなら、1年やそれ以上の月日をかけて、ブドウを育てるところから始める人たち。
皆さんが、大切に育てたり、苦労して自らの味わいにしたりしてきたものばかりです。だからこそ、最後まで捨てずに役立ててほしいという生産者の皆さんの想いと、私の想いがつながりました」
人との出会いも大切に。手から手へ、バトンをつなぐように生み出される『BetulaN』の色。それはまさに、“北海道をそのまま映し出したような生命力あふれる色”。手染めで一度に少しずつしか染められないため、注文によっては何日も同じ素材と向き合うことになります。
その日々を「染めるたびにドキドキして、飽きることが全くない」と語る、野口さん。
「ワインづくりの過程で残った果皮と白樺は、とくに難しくて、ドキドキしますね。
なぜならワインの場合、ブドウの種類が同じでも、ワイナリーごとに醸造の仕方がちがいます。すると、果皮に残る色も全くちがうんです。白樺の場合は、同じ種類でも持っている色素が木によってちがう。だから同じg数で染めても、どうしても色がブレます。
色がブレるということは、染色職人の世界ではマイナスです。なぜなら、均一に染まる化学染料を基準にしているから。
でも天然染めは、自然から生まれたもので染めるのだから、一つとして同じものにならないことが当たり前です。ワインが、同じブドウでもワイナリーごとに味わいが全くちがって、それぞれがすばらしいように。自然のものだからこその個体差を理解して、使い込むうちに少しずつ増す風合いもたのしんでいただけるように。使う人の日常を想像しながら染めています」
野口さんは、染料の保管や下準備にも心を砕きます。それは料理と同じように、食材の保存や下ごしらえもきちんとしてこそ、「おいしい」ものに仕上がるから。
「天然染めは、材料選びから、保存、下処理、染色と、一つひとつの工程のさじ加減で現れる色が微妙に変わるので、どこか料理と似ていますね。だからこそ、職人の腕と経験も問われます。
たとえば白樺の内樹皮は、夏に間伐されたものを使用します。なぜなら私たちが染めに使う内樹皮が、この時期のものしかキレイに剥がれないからです。一年のうちでも限られた時期のものだけを譲ってもらうので、葉が枯れないように陽光の当たらない室内で管理します。また、内樹皮は染める前に熟成させたり、枝はハサミを使ってなるべく細かくカットしたりすることも欠かせません。
また、使う水も重要です。『野口染舗』では地下水を使用しているのですが、これは初代の頃から。古くから水に恵まれた土地であったことが、創業の地として選んだ決め手になったようです。
あとは、素材から不純物を出す下処理の『精錬(せいれん)』と、色を入りやすくするためにたんぱく質を加える『濃染(のうせん)』も重要。下処理をきちっとしないと、色の入り方はちがってきます」

- 白樺の内樹皮から煮出した染料は、まるで朝焼けのような色
一つひとつが最終的な出来に大きく関わる、積み重ねの連続。丁寧に手順を踏み、煮出されて現れる素材本来の色。それは、表に見えていた色からは想像がつかない場合も少なくないそうです。
「白樺の内樹皮は、なんとも言えない落ち着いたピンク色、枝はオレンジ色や赤みを帯びたブラウン、葉っぱは黄色に染まります。白い外樹皮とは全くちがいますよね。そして同じ一本の木でも、部位によって色がちがうのも自然のおもしろさだと思います」
味わいを、じっくり引き出すように。鍋で色を煮出し、そこへ生地を静かに浸す。すると、具材に味がしみ込むように、素材の色が生地に移り、少しずつ染まってゆきます。それはまさに料理のよう。さらに色を定着させる『媒染(ばいせん)』を施すことで、色は独特の光をまとい、一層輝きはじめます。
その様子を「息吹で、染める」と表す野口さん。
「『BetulaN』は、自然がもたらす生命力を、染めものを通してふたたび宿すものづくりをしています。それは北海道という土地にしかないものであり、顔の見える生産者さんがいる、ストーリーのあるものづくりです。
同じような色が出たとしても、ものに背景があるかどうかで、感動のレベルは全くちがうと私は考えています。やはり感動のあるものは愛着も湧きますし、ほかに替えのきかない唯一無二になるはず。
『BetulaN』の染めものが、そんな体験をどなたかに届けるものになればと願っています」
- NEW<2026年1月13日(火)第三弾発売>大地の余韻を宿す「葡萄染め」のバッグ
-
北海道のワイナリーで役目を終えた「葡萄の果皮」を使用。
広い空と畑が滲み出たような穏やかな色合いです。

- <第二弾>※全色、完売しましたカフェの一杯から生まれる
「コーヒー染め」のバッグ - DEAN & DELUCA のカフェで抽出された後のコーヒー粉を使用。焙煎具合によって変化する染液の色合いや、媒染の違いにより生まれる美しさをおたのしみください。

- <第一弾>※全色、完売しました暖かな陽光のような「白樺染め」のバッグ
- 北海道蘭越町で間伐される白樺の、内樹皮・枝・葉を使用。
丁寧に抽出された、北海道のやさしい日の光を感じる色です。











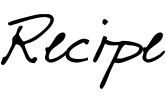 つくるたのしみ
つくるたのしみ