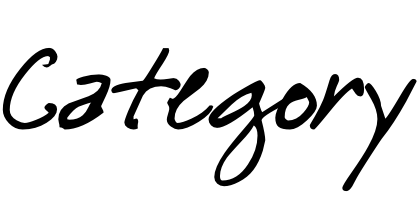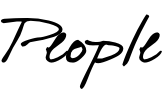 想いをつなげる
想いをつなげる

古くからあるレシピをもとに、時代に寄り添った新たな価値を生み出す。つくり手の創意工夫が込められた「おいしい」との出会いは、食するよろこびの一つです。
世界三大料理としても知られる「中国料理」も、世界各地でさまざまな味わいが育まれている伝統料理です。日本では「中華料理」とも呼ばれ、北京、上海、四川、広東など、地域によって味も調理法も多彩。また、高級なものから庶民的な一皿まで、レシピはまさに星の数ほどあると言っても過言ではありません。
この中国料理に、新たな風を吹き込む存在としても知られる『O2(オーツー)』大津光太郎シェフ。中国料理の魅力や想いを伺うため、訪ねました。
INTERVIEW
『O2』大津光太郎シェフ

- 菜切包丁のような大きな刃の中国包丁で、シェフ自ら仕込みをする。
国産を始め、現地からも直接仕入れる厳選食材を使い、型にはまらないおいしさで評判の『O2』。夜営業のお店へ伺ったのは、さんさんと太陽が注ぐ11時。扉を開けると、仕込み真っ最中の大津シェフが迎えてくださいました。カウンターの中を覗き込むと、キュウリ、ミョウガなど、旬の野菜がその手元で素早く端正に刻まれてゆきます。
「中国料理は、一瞬でおいしさが決まるのが魅力です。だから、仕事の9割は仕込み。食材を刻む、油通しする、包むなど、全てのメニューをあらかじめ仕上げる直前まで用意しておきます。炒め物はとくに一瞬。僕は営業中、5分も鍋を振っていないんじゃないかな。その分、午前10時には店に入って仕込みを始めます」

- 店からほど近い、深川生まれの大津シェフ。その料理を始めたきっかけから伺う。
「母が他界したのは、僕が小学5年生のとき。会社勤めをしていた父は40代で、仕事がとくに忙しい時期でした。だから自分で料理をつくっていたんですが、そのうち『どうしたらおいしくなるんだろう?』と考え出したのが、料理の道を目指した理由です」
自宅に併設した美容室で美容師をしていたお母さまは、料理上手。毎日3食、お弁当もおやつもすべて手づくりで、おやつに出たレアチーズケーキがとくにおいしかったと振り返ります。
「最初に『どうしたらおいしくなるんだろう?』と考えたのは、卵かけごはんです。ごはんに醤油を先にかけたほうがおいしいんじゃないかとか、素材の組み合わせとかを追求しましたね。小学6年生で一味唐辛子にハマったときは、卵かけごはんを真っ赤にしてヒーヒーいいながら食べていた記憶があります」
料理を始めたころから、自分なりに工夫し、味わいを広げることが好きだったという大津シェフ。高校時代は野球漬けでしたが、休日は料理をするなど「職業にするなら料理人しかない」と決めていたそうです。

- アラカルトで出している焼売を蒸すせいろ。『O2』の焼売には、ソーセージをヒントに、ハーブやスパイスが練りこまれている。
そうして、調理専門学校へ。フレンチを志していましたが、1年生で取り組んだ調理実習で一番おいしく出来たことが、中国料理の道へすすむきっかけに。2年生のときに講師と生徒として出会った『トゥーランドット臥竜居』脇屋友詞シェフに感銘を受けます。
「1年生の終わりに作品をつくるのですが、そのときに手に取った本が脇屋さんのレシピでした。ヌーベルシノワの先駆けだった『トゥーランドット臥龍居』の料理を見て、僕はフレンチをやりたかったけれど、中国料理でもこういうスタイルがあるんだって衝撃を受けましたね。その後、学校で教えていただき、脇屋さんのもとで働きたいと就職しました」
- *ヌーベルシノワ・・・フランス語で “新しい” を表す「nouvelle(ヌーベル)」“中国の” を表す「chinois(シノワ)」を合わせた新スタイルの中国料理。各料理を西洋料理のようにに美しく盛り付け、コース料理と同じように料理を提供する。油の使用量を減らし、素材の味を活かすように調理することも特徴のひとつ。
最後まで「おいしい」ひと時を
料理人として、ずっと中国料理ひと筋に歩んできた大津シェフですが、いまだに現地へ行くと新鮮な気持ちになるそう。
「中国料理は、同じ食材でも地方によって使い方が全然違います。『O2』ではハーブをけっこう使っているので、南のほうをイメージしているんですけれど。料理の数があまりに多すぎて、僕の人生最後まで、全部を知らないで終わっていくんだろうと思うほどです」

- 夜に向けてセッティングされたテーブル。カウンターとテーブル席で料理とナチュラルワインがたのしめる。
現地での学びと素材の味わいを活かしたコース料理は、フカヒレの姿煮や牛ホホ肉の煮込みがメイン。合わせるワインは、フランス産のナチュラルワインが中心で、中国茶も揃います。また、焼売やチャーハンなどのアラカルトメニューも。
これら全ての味わいで、もっとも大事にしているのは「抜け間と、最後の余韻」。
「中国料理の味付けは、基本的には輪郭をはっきりつけると学校で教わります。ただ、ひと口食べたときにはすごくいいけれども、トータルで食べたときにどうなのか。全部の料理がはっきりしていると、食べ疲れたり『中国料理は重い』と言われるんじゃないかと、僕は考えていて。
だから基本は押さえつつ、そこにハーブやスパイス、柑橘など、ひとつ何かをプラスする。それによって、軽やかに食べられるのが、うちらしい中国料理だと思います。ひと口ではなく、全部食べ終わったときに、トータルでおいしかったと思っていただけるものを目指しています」

- 中国料理ではなじみのスパイスやハーブだけでなく、爽やかなレモングラスも使う。
欠かせない食材である国産のハーブ類や柑橘は、必ずつくり手のもとを訪れ、顔と顔を合わせたものを。食材が育つ環境を見るだけでなく、お互いに共鳴する付き合いを大切にしています。
「農家さんと料理人。ものありきですが、やはり付き合いは人と人です。『この人のものを使わせてもらいたい』と思いたいですし、反対に僕も『使ってほしい』と思ってもらえる魅力を持っていたい。そのためにも、おもしろいと感じた直感を大切に、実行にうつすことを心掛けています。
たとえば、お手伝いに行っている宮城のワイナリーで出会った、広島の『梶谷農園』さん。基本的には新規では受けていらっしゃらないと聞いたのですが、少し話したらおもしろい方で。訪れてみたくて、2週間後に遊びに行きました。そのときに、30分くらい農園の見学をして、1時間半くらい梶谷さんの息子さんとドッヂボールをしたら、使わせてもらえることになったんです。
初対面で『今度ごはんに行きましょう』って言うでしょう。僕はその場で『いつにします?』って決めちゃう。そうじゃないと、絶対に次はありません。考え込む前にやってみることで開ける道もありますから」
お客さまの笑顔が積み重なって今がある
オープンキッチンから客席を見つめる視点にも、脇屋シェフのもとで得た学びが活かされているといいます。それは、一瞬で仕上げる中国料理だからこそ、お客さまに寄り添えること。
「脇屋さんからは、先を読む大切さも教わりました。2手、3手先を読んで、何か作業しながらも次のことを考えます。
どんな料理もそうかもしれませんが、中国料理は出来たてがいちばん。『トゥーランドット臥龍居』時代、営業中は『お客さまが今グラスのここまで飲んでいるから、このタイミングでドリンクを伺いに行く。だから、次の料理は提供するのを一歩遅らせよう』というのが普通でした。
僕は『たのしかった』と言って帰っていただくのが何よりうれしい。だからこそ、料理の質を高めるのはもちろん、お客さまによりよいサービスをしたいと思っています。そのためにも営業中の効率にこだわって仕込みますし、コース料理メインなのも提供時間が掴めてサービスに注力しやすいからです。コース内容の組み立ても、2手、3手先が読めるように、必ず蒸し物を入れるなどして構成しています」

- カウンター越しにお客さまと会話したり、笑顔が広がってゆく様子を見るのもうれしい。
他にはない味わい、大津シェフの人柄、そして心地よいサービス。「今日もたのしかった」と、その時間を反芻するしあわせに、多くの人が惹きつけられてやまないのでしょう。
「ありがたいことに、毎日多くの方が店に食べにきてくださって、僕自身、現状が出来すぎていると感じています。そもそも『O2』が今の方向性でよいと感じられたのは、店を始めて2年くらい経ったころなんです。出身店の前評判で来店してくださる方は少なくありませんでしたが、これでいいのか? と、自信が持てませんでした。でも、お客さまが笑顔になってくださる様子が少しずつ積み重なって、勇気を持てたんです。
僕にとって『食』は、人を笑顔にするもの。食べるのも料理するのも同じくらい好きですが、やはり料理人としてうれしいのは笑顔を見る瞬間です。家族や友人ではない誰かを幸せな気持ちにさせるって、ふだん生活をしている中では滅多にありませんから」
これからも、お客さまを目の前にしていたい。その上で、新たな取り組みにもチャレンジして、得たものをまた店に活かしてゆけたらと、大津シェフ。笑顔を生む心地よい中国料理が、今日もまた誰かのひと時を彩ります。

- 大津 光太郎|KOTARO OOTSU
- 1982年、東京・深川出身。『O2』オーナーシェフ。東京の名店『トゥーランドット臥龍居』で約15年間腕を磨き、2018年に清澄白河に『O2』を開く。基本を押さえつつ、四季折々の国産の材料や香りのよいハーブ、柑橘などを使った新感覚の組み合わせや味付けで話題に。野菜ソムリエの資格ももつ。
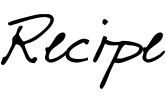 つくるたのしみ
つくるたのしみ