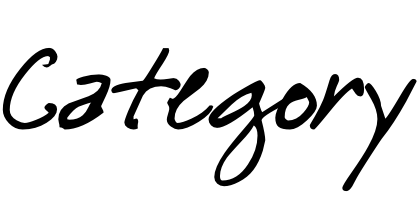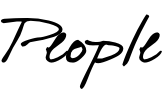 想いをつなげる
想いをつなげる

DEAN & DELUCA(ディーン & デルーカ)では、気軽にレストランのような一品を味わっていただきたいと、様々なシェフと缶詰料理に取り組んでいます。
その中で、東京・神田のレストラン「the Blind Donkey(ザ・ブラインド・ドンキー)」のジェローム・ワーグさんとも、ご縁ができました。
ジェロームさんがシェフを務めるザ・ブラインド・ドンキーは、和食の精神を重んじ、旬を大切に。全国のつくり手から届く食材を活かした、滋味深いメニューを提供しています。現在は、自然豊かな徳島県神山にも居を構え、地元食材などを使った瓶詰め料理や調味料も手掛けています。
口にした人から「優しい味」と言われることも多いという、その料理は、どのような背景や想いから生まれているのでしょう。ジェロームさんに、お話を伺いました。
INTERVIEW
「おいしい」にはストーリーがある
ザ・ブラインド・ドンキーのウェブサイトには、このようなメッセージが掲げられています。
地球はわたしたちの“庭”です。その庭を耕すことで、わたしたちは生命を育んでいます。生きとし生けるものにとって、この庭はすこやかで、安心できるものでなくてはなりません。そのおかげで、わたしたちの人間らしさが約束されているからです。
食を取り巻く、あらゆるもの。育てたり獲ったり食べたりする、私たち “人間”も含めて“自然”の一部である。そして、自然がすこやかであるからこそ、私たちは食するよろこびを味わえる。
ともすると難しくなりがちなテーマですが、ジェロームさん曰く「地球にとってよいものが、おいしくないわけがありません。つまり、本当においしいものは、地球にとってもよいものなのです」。そして、その「おいしい」には、確かな理由があると続けます。
「おいしいものは、どこからどのように来たのか、ストーリーがつながっています。誰が、どこで、どのように育てたのか。どのように獲り、さばいたのか。そして、どのような食材を使い、どのように加工したのか。だから僕は必ず、どこの農家さんや漁師さん、畜産家さんから、どのように届いているのかがわかる、ストーリーのある食材を使います」
そうして仕立てられたザ・ブラインド・ドンキーの料理は、全て生産者さんと料理人の共作。半分は生産者さん、半分が料理人の作品だと、ジェロームさんは考えているそうです。
料理人は食材のストーリーを伝える紡ぎ手
ジェロームさんは、料理上手なお母さまのもとパリで生まれ、南フランスのプロヴァンス地方で育ちました。今のような考えに至ったのは、アーティスト活動の傍ら、カリフォルニアのレストラン「シェ・パニース」でシェフとして働きはじめ、30代になってから。
「南仏にいたころは、オーガニックの野菜がうんぬんとか、よい食事とか、考えたこともありませんでした。なぜなら、食材に恵まれているのが当たり前でしたし、母が料理上手で、食事がおいしいのも当たり前。問題意識を持つようになったのは、カリフォルニアで働き、アーティストとして食材について考えるようになってから。30代を超えて、当たり前のようにいい食事にありつけていたことが普通じゃなかったと気がつかされたのです」
シェ・パニースでの、ある農家さんとの出会いも大きいといいます。
「ボブ・カナールさんからは、大きな影響を受けました。彼は、野菜を育てる農家であり、詩人であり、科学者でもある。土についての考えや知識が素晴らしくて、地球全体を包括した、とても興味深い話をしてくださるんです。彼曰く『土が肥沃でないと、何も育たない』。ああ、本当にその通りだと感じ、僕は自分の会社を『Rich Soil(リッチ・ソイル)』と名付けました」
ジェロームさんのお話の端々からは、常につくり手への敬意と共に、料理へ向き合っていることが感じられます。また、それと同じくらい旬を大切にしていることも。これらを象徴するのが、新しいメニューを考えるとき。
「僕は、ファーマーズマーケットなど(つくり手と)対面できる場で、それぞれのつくり手が育てる野菜の旬を聞きます。場合によってはリストアップしてもらったりして。そうすると、中には一年待つ場合もあって、収穫するという知らせがくると『ああ、やっとこの季節になった』と、とてもうれしくなります」
旬とひと口に言っても、四季折々、地域により様々な気候をもつ日本列島。南フランスとカリフォルニアという、温暖で似たような気候をもつ2か所がベースにあるジェロームさんにとって、日本の旬を掴むのは難しかったそうです。
「夏の前に梅雨があるのも違いますし、日本は小さな国なのに、九州から北海道まで季節が届くのに2ヶ月かかったりするでしょう。だから、たとえばトマト一つにしても、台風の前には収穫するところもあれば、北海道だと10月まで収穫できるものもある。どっちが本当? と。でも、理由をそれぞれの農家さんに聞くと、納得できる。どれが間違っているというのはないんです。
だからこそ、やはりストーリーがとても大切。『今日のトマトは、どこの土地の、誰が、どのように育てたか』。それを知ったうえで、料理して、お客さまに味わっていただき、伝える。これが僕の役割です」
おいしい一皿をつくるプロフェッショナル。その大前提のもと、扱う食材の一つひとつを細やかに把握し、選び、最もおいしい状態に仕上げる。料理人というのは、つくり手の日々や想いまで伝える力を持ち得る、ストーリーの紡ぎ手なのだと感じさせられます。
文化としての加工品づくり
これまでの料理やスタイルを伺うと、旬の食材を素直に調理して、出来立てを味わう。そんな、自然と共にある形がジェロームさん流かと思いきや、日持ちのする瓶詰め料理や缶詰料理などの加工品も手掛けます。なぜ、加工品をつくり始めたのでしょうか。
「そもそも、僕がつくるピクルスやケチャップ、そして今回の缶詰料理は、昔からあった料理方法です。料理という大きな流れでいえば、全く別のことをしている意識はありません。むしろ重要だと思っています。
これまでのように来店していただくのが難しい今、レストランを続けていく方法を模索しています。その中で、いろんな加工の文化を活かした料理を、文化の一つとしてつくっていきたいのです。
また、これは今のご時世に関わらず、たとえば農家さんなら、見た目の悪いものができたり、豊作過ぎてかえって困ったりといった状況は、必ず起こります。そういうときに、料理人である僕に何ができるかと考えたら(加工品という料理に)つながりました」
長期保存がきき、遠方にも届けられる。加工品のメリットを活かし、おいしい一品に仕上げ、食材の未来をつくる。つくり手はもちろん、食べる側にとってもうれしい。それが、ジェロームさんの手掛ける加工品なのです。
レストランから伝えていきたいこと
最後に、今後について伺いました。すると「まずはこれからも、レストランを続けていきたい。そして、将来的には、レストランを食べるだけでなく文化的な場所にしていきたい」とのこと。そのためにも、今はザ・ブラインド・ドンキーで食材を購入できるよう整えたり、店内に関わりのある農家さんを記すマップを掲げたり、つくり手とのトークイベントを企画したりと、活動はますます多岐にわたっています。

- ザ・ブラインド・ドンキーの外に設けられた、買い物できるコーナー。
これからも、食するよろこびを伝え「おいしい」をたのしみ続けるために。料理人として、何ができるのか。ジェロームさんは常に考え、その時々にできることで届け続けます。私たち、メッセージの受け取り手は、そのおいしさをたのしむ。料理人の一皿を味わうことも、未来をつくる要素の一つです。

- ジェローム・ワーグ|Jerome Waag
- フランス・パリで生まれ、自然豊かなプロヴァンスで育つ。オーガニックレストランの先駆け「Chez Panisse(シェ・パニース)」にて総料理長を務める。日本には2016年より移住。目黒で「BEARD」を営んでいた原川氏と共にRichSoil & Co.を立ち上げ、2017年に「ザ・ブラインド・ドンキー」をオープン。お店でつくる「Donkey at Home」と名付けた加工品シリーズも手がける。






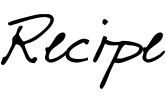 つくるたのしみ
つくるたのしみ