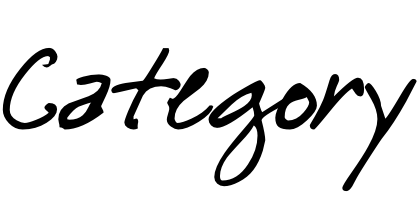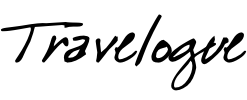 僕らの新しいローカリズム
僕らの新しいローカリズム

僕らの新しいローカリズム|北海道 美瑛・東川
小麦、じゃがいも、とうもろこしなどの畑がパッチワークを織りなす丘の町・美瑛(びえい)。
そのお隣で、大雪山連峰に育まれた清冽な地下水が生活水、という水の町・東川。壮大な山岳、森林、河川に恵まれた両者は、古くから写真カルチャーが息づく土地柄でもある。旭川空港から、美瑛は車で15分、東川は10分。じつは大都市からのアクセス抜群なこの地では今、新しい人々がさまざまな食文化を持ち込み、それぞれの世界観を創っている。
写真/伊藤徹也 文/井川直子
CHAPTER 19『Lienfarm(リアンファーム)』
農薬を使わなくても、虫がつかないのは
美瑛川を真ん中にして、美瑛の丘と対面しているのが西神楽の丘。
『Lienfarm(リアンファーム)』の畑は標高200メートル付近の、朝日を受ける東向き斜面に広がっている。春から秋にかけて約60種類ものハーブたちが競うように背を伸ばし、絢爛に花を咲かせるという、そのすべてがオーガニックだ。
畑に立つと、足がふっかりと土に沈んだ。訪れたのは晩秋だが、それでも歩き進むにつれてさまざまな香りが漂い、まるでハーブたちが挨拶してくれているようだった。
農薬を使わなくても、『リアンファーム』のハーブには虫がほとんどつかない。
なぜだろう?
訊ねると、代表の石田佳奈子さんは「森があるからじゃないかな」と答えた。
顔を上げて見回すと、畑を守るかのごとく、ぐるりと森。白樺、トドマツ、アカエゾマツ、エゾヤマザクラ。北海道ならではの、寒さに強い針葉樹と広葉樹である。
「虫は生息しているんですよ。でもそれを食べる虫もいて、それを食べる小動物、それを食べる鷲や狐がいる。動物たちが糞をすれば微生物の餌になる。生態系のバランスが取れているから、わざわざ畑のハーブを食べる必要がないのでしょうね」
話しながらも瞬時に花を選り分け、手早く、そして優しく摘んでいく。
石田さんは、植物療法先進国のフランスで有機農業と蒸留を学んだ、生産者であり蒸留家。2018年から自家栽培のハーブや森の樹木、野草から、ハーブティー、精油、蒸留水をつくり、ハーブソルトなどの調味料も手がけている。
「食材を超える存在」になるハーブ
石田さんが植物に興味を持ったのは、大学時代のオーストラリア留学がきっかけだった。
日本でまだ“オーガニック”が高級食材だった2003年当時、ホストファミリーは野菜でもハーブでも、あたりまえのようにそれらを暮らしに取り入れていた。
「植物は、人間の身体と深く関わっている。そこに興味を持ちました」
地球環境に負荷を与えず、調和して育った植物は、それを口にする人間にもまた負荷を課さない。それどころか身体をつくり整える、食材を超える存在になってくれる。
そもそも人間は、昔からそんなふうに植物と支え合ってきたのではないだろうか?
その真理を知りたくて、帰国すると文化人類学から歴史を紐解き、植物療法としてのアロマセラピーも学んだ。
「でも日本では、アロマセラピーの原料であるハーブを識るには限界がありました」
そこで2005年に渡仏。語学を習得した後、ジュラ地方にある農業省認定の農業学校でハーブを専攻。在学中にも20軒近くのハーブ農家を訪ね歩いた。
その中で、ハーブの栽培から高山での野草の採取、蒸留まで全工程を手がけていたルソー氏とボイヤー氏に師事。彼らが実践する伝統的な精油製造技術を習得し、やがてブルターニュ地方に自分の農園を持った。
チャレンジを終えて帰郷したのは2017年。じつに12年間、フランスで植物と人間の関係を多角的に捉えてきた知見が、『リアンファーム』のハーブと、そのプロダクトに注がれている。
植物にも意思がある
ハーブにはハーブの栽培メソッドがある。それをもし野菜と同じように育てると、大体において香りは弱くなってしまう。
「フランスでは厳しい条件で育て、ハーブ自身の生きる力を養います。子育てと同じですよね。あまり干渉しすぎるとか弱く育つので、観察して、手を加え過ぎないよう見極めるんです」
『リアンファーム』では、太陽の動きや月の満ち欠けなどに則って栽培するバイオダイナミック農法と、微生物(EM)を使った自然農法を組み合わせている。倒木した木や落ち葉を畑にすき込み、石灰や昆布なども与えて土壌を養うのだ。
あとは西神楽の自然が、植物をたくましく育ててくれる。
マルセイユとほぼ同じ北緯43度で、湿度は低く、夏と冬とで寒暖差は30度以上にもなる風土。この厳しさから、植物は身を守るために芳香成分を量産する。
つまり香りが強くなる。
植物の力は香りが強いほど高まるとされ、ピークに達するのは開花直後だ。
「摘み取る時期の見極めも、花を揉んで枝を落とす作業も、精油を抽出するタイミングも、ほとんどの判断が“感覚”です」
摘み取った後は低温で乾燥させ、日光に当てず、粉砕もしない。
ストレスなく完成したハーブティーはえぐ味が出ず、精油の香りは10年も持続するという。
「植物にも意思がある。なんとかして子孫を残そうとする植物は、自らの種取りを人間にさせることで、目的を果たしています。人間は効能を与えてもらう代わりに、彼らの存続を手伝っている。お互いに助け合って、共存しているのです」
冬はカフェになるトレーラーハウスで、『あたため茶』をいただいた。
エルダーフラワーやジャーマンカモミールなどの甘やかな香りの中に、凛とした森の気配がする。じんわりと温まる。それは液体の温度で温まるのでなく、血が巡るような、自分の身体が動き始めたような温かさだ。
このままの地球を次の世代には渡せない
植物を学ぶきっかけは留学だったが、遡れば、子どもの頃から素養はあった。
「正義感の強い子で。地球の環境破壊とか人間の健康被害とか、真剣に心配していたんです。このままじゃ地球が危ないとわかっているのに、どうして世界はそっちに進むのか。自分にできることはなんだろう?って」
石田さんは、こう考えた。
いちばん大事なのは健康で、人間は食べて生きる動物だ。けれど食べ物をつくる農業は、利益が目的になると、量産のために化学肥料を使う。すると虫がつきやすくなり、農薬でコントロールする。
それが現代の利益追求が招いた悪循環なら、農薬がなかった時代の暮らしに立ち返ればいいのではないか?自分たち家族が食べていける分だけの小さな農、手に負える範囲でまかなう暮らし方に。
まずは自分がそれを実践し、発信して、いいなと思った誰かが真似をしてくれたら。それが少しずつでも広がった先に、未来が見えた。
「私の最終目的は、地球の永続です。このままの地球を次の世代には渡せない。子どもが生まれていっそう強く、そう思います」
6年前、石田さんがたったひとりで西神楽の畑を開墾した当時、じつは妊娠中だった。ちょうどジャガイモの種を植えていた時に陣痛がきて、生まれたのが息子の燈(あかり)くんだ。
「明け方に出産したんですけど、朝日がものすごく美しかった」
彼は畑に立つ母の背で眠り、ハーブの香りに包まれて育った。四季折々の花や生きものと遊び、水やりを手伝い、収穫したハーブをおいしく食べたり飲んだりする。
6歳の彼にとって植物と共存する暮らしは、生まれる前から「あたりまえ」だ。

- Lienfarm(リアンファーム)
-
ハーブは有機JAS認証取得。石田さんは英国IFA認定アロマセラピストの資格も持つ。冬季(11〜3月)のみカフェ営業あり。2025年春に化粧品をリリース予定。自社製品と、ルソー氏・ボイヤー氏の輸入精油は オンラインショップ より購入可。
北海道旭川市西神楽南16号356
TEL| 090-6800-7649
営業時間|カフェ10:00〜16:00(11〜3月のみ、オープンデイとして不定期開催)
※ Instagram にて要確認。できれば予約を。
NEXT CHAPTER
「僕らの新しいローカリズム」北海道の東川・美瑛編は全6回。
第5回は、料理家のたかはしよしこさんが営むカフェレストラン『SSAW BIEI』です。美しい丘が連なる美瑛へ、2020年に東京から一家で移住。ますます楽しげにパワーアップした家族との暮らし、土地の四季を映す料理とは?
次回は、2025年5月13日フラワームーンー 毎月、満月の日に新たな記事を更新
CHAPTER 20 coming soon