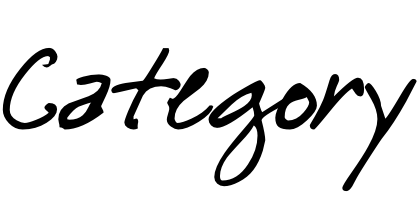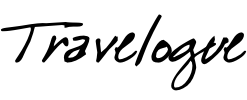 僕らの新しいローカリズム
僕らの新しいローカリズム

僕らの新しいローカリズム
地方が動き始めている。
都市では「食材」や「原材料」と呼ばれるものが
田畑で実り、山に生え、風土の中で生きている場所は、
食べものづくりの人々にとって、刺激に満ちた“現場”なのだ。
ローカルという現場に立つ彼らは今、都市ともゆるくつながりながら
暮らしを映す食や酒、共感で結ばれたコミュニティを生んでいる。
新連載「僕らの新しいローカリズム」、スタートは北海道・函館編から。
石畳の坂道に洋館が建ち並ぶ港町風情と、雄大な自然が静かに溶け合う
この地に惹かれたつくり手たちを、全9回にわたってお伝えします。
写真/伊藤徹也 文/井川直子
CHAPTER 05『コルツ』後編
2023年夏、『コルツ』のディナー全9皿
1.「グリーンアスパラガス 百合根と卵のサラダ」
2.「水茄子のカツレツ」
『清和の丘農園』の美しく強き水茄子。揚げればさらに迫力を増し、衣はカリッと、中の緻密な果肉はとろとろになる。
むいた皮もゆでて添え、水茄子のすべてを味わう一皿。合わせたリエットは、定番の肉ではなく、なんと海の鯖。函館沿岸で捕れる鯖を、『
あかり農場
』の豚肉から作る自家製ラードでゆっくりと煮た、軽やかなリエットに仕立てた。
ラードは、塩豚(豚肉を塩水で煮詰めた常備食材)を作る際に浮いた脂を利用した副産物。これまた上質な「旨味の塊」である。
3.「山羊のフレッシュチーズとセミドライトマトのカプレーゼ」
4.「松皮鰈(まつかわがれい)のタルタル」
「魚の皮も肝も骨も、すべてを食べてもらいたい」
身は小さな角切りで、きびきびとした食感。皮と肝は日本酒を加えてゆでた後、胃袋はさらに洗い、皮はしっかりと冷やしてゼラチン質を締め、タルタルに。
骨(アラ)は、秋冬に干した山の茸や大根を加えて濃厚なスープになる。
添えていたのは、オクラと花(清和の丘農園)だった。
生オクラの青っぽさとサクサク、鰈の身のもちもち、皮のコリコリ。歯ごたえの重奏を楽しみながらスープを流し込めば、口の中で海と陸の風土が完成する。
取材時の魚は南茅部産の松皮鰈だが、冬はカジカ、春先の真子鰈(まこがれい)では卵も加わる。
緑もアマランサス(ヒユ)の葉、葉山葵、在来種のクレソン、山葵菜など季節で巡る。
長年作り続けるこの皿は、佐藤さんのライフワークといえるかもしれない。訪れる度に、違った顔を見せてくれる。
5.「枝豆のラビオリ」
絶対にフォークで刺さず、1個をひと口で。途端に、薄くしっとりとした生地の中から、極限までやわらかな枝豆のピュレが溢れ出す。
枝豆の清々しい香りとコクは、『清和の丘農園』ならではの芯の強さ。真昆布だしのミネラル感が、枝豆に不思議なほどしっくり馴染む。
天然真昆布は古くから、北海道でも函館沿岸で採れる、地元の食文化だ。しかし近年の環境異変で、天然昆布は減少の一途を辿っている。
佐藤さんのスタンスは、「自然から奪い過ぎない」こと。
天然、自然、伝統。そういったものを継いでゆくためにも、人間の技術向上による養殖も選択肢に加え、必要な皿に、必要な量だけ、必要なものを施している。
6.「冷製オレキエッテ 夏野菜のタルタル」
万願寺とうがらし、緑茄子、丸茄子、きゅうり、フィノッキオ(ういきょう)の茎と葉、ズッキーニといった緑の野菜に、ミョウガも少し。
それらを、粘り気の強い函館特産のがごめ昆布の粉末でつないでタルタルにし、ショートパスタで食べさせる。
載せた雲丹は、濃厚なのに後味さわやかな奥尻産。
以前は産地から仕入れていたが、現在では函館の鮮魚店から買っている。
「僕は『
中島廉売
』と呼ばれる市場の近くで育ったんです。昔は毎日お祭りのような賑わいだったのに、お店も人もどんどん消えていきました。
だけど今、あらためて、市場や魚屋で買う意味を考えたい。天候や海の状況、今日の魚の話などをやりとりしながら買うことが、自分の中でとても大事になっています」
ただし、移転した場所は漁港にも近い。今後はこちらにも足を運び、馴染みになった漁師から買うこともあるだろう。
鮮魚店、市場、港(漁師)。函館ではどれか一つでなく、どの選択肢も日常の中にある。
7.「鮎、グリーントマトのケッカソース」
ナスタチウムの葉陰で、山の渓流を泳ぐような鮎の皿。福々しい天然鮎は、清流・天の川が流れる上ノ国で知人が釣り上げたものだ。
鮎といえばきゅうりを連想するけれど、『コルツ』では同じ緑でもグリーントマトであった。ケッカソースとは、トマトで作る冷たいソースのことである。
完熟したグリーントマトに塩と蜂蜜を少々振り、ザルに揚げてゆっくりと水分を落としていく。こうして味を凝縮させた果肉に、温めたニンニクオイルをかけて混ぜる。それだけで、バルサミコ酢やヴィネガーを使わずとも、酸味と甘味、みずみずしさが生きたソースになる。
ちなみにトマトから落ちた水分のほうは、ガスパチョという、トマトの「旨味」を味わう冷製スープとなってあますところなく生かされる。
8.「ジビーフとリコッタサラータ」
しっとりとしているが、しっかりと噛む肉だ。そして噛むほどに、ずっと噛んでいたくなる旨味である。
その肉焼きは独特で、オーブンで下焼き後、さらに温かい土鍋で2時間以上休ませる。最後にフライパンで焼き目をつければ、香ばしさと、しっとりとした食感がともに際立つ。
「ジビーフ」とは、日本では数少ないオーガニック認定の牛肉である。
北海道南部、様似(さまに)の『
駒谷牧場
』は、日高山脈の麓に広がる雄大な土地を持つ。牛たちは四季を通して山や森、草原で放牧され、小川の水を飲み、自然交配によって子孫を増やす。野生のジビエのようなビーフ、だから「ジビーフ」。
「壮大過ぎて、びっくりしますよ。牛が、あの巨体で崖をぽんぽん飛び回ったりするんです。雪を掘ったり、木の幹をかじったりもする」
崖を飛ぶ牛……。
彼らは畜産家の西川奈緒子さんが一人で育て、滋賀『
サカエヤ
』の新保吉伸さんによる適切な“手当て”が施された後、シェフへとつながれる。手当とは個体差を見極めて肉をカットし、必要に応じて水分の調整や熟成を施すなど保管方法を変え、いわば料理人に合わせて「調律」する仕事。
「牧草だけを食べて育った牛はこれまでも使ってきましたが、多くの場合季節でムラがあり、匂いも強い。だけどジビーフは臭みが全然ないんです」
佐藤さんの言葉で言えば、「ピュアな味」。
そこでソースの代わりに、チーズ工房『
白糠酪恵舎(しらぬからくけいしゃ)
』のリコッタサラータを添えた。塩味の強いチーズなので、ふわっと削ってほんのりと。
添えた野菜は、夏ならば赤紫蘇。赤身の肉と赤紫蘇は、不思議なことに香りの余韻が同調した。
9.「ブルーベリー、レアチーズ、ビスコッティ・サボイアルディ」
ビスコッティ・サボイアルディ(軽い食感のビスケット)が、不揃いな形で連なる様は「丘」を、ミントの葉は「森の木々」を想わせる詩的なドルチェ。
無農薬栽培のブルーベリーは、北斗市の『
ハウレット農園
』から。
カナダ人のピーター・ハウレットさんが1990年に開園し、現在は息子であるハヌルさんとパートナー、その子どもの3人で営むこの農園では、農薬・除草剤・化学肥料を一切使用せず、草刈りも収穫もすべて手作業。
人の手で丁寧に、7種類のブルーベリーと野生品種に近いカシスを育てている。
「お父さんもそうでしたが、息子さんもすごく素敵な方。素材に人柄なんて出ないって言う人もいるけど、僕はやっぱり表れると思う」
優しい味わいと思いきや芯の強さを感じる野菜、野生的でも洗練されている果実。お酒や肉だって、人の手が関わるものにはつくり手が投影される。
そう佐藤さんは言うけれど、それは彼が、いつも会って言葉を交わしているからだ。
つくり手がどんな人柄で、今何を考え、どう取り組んできたのか。わかっている料理人だから表現できる、境地がある。
私はただ『コルツ』の料理を「おいしい、おいしい」と食べるうち、函館の風土を想像し、帰り道ではなぜか自分の暮らす街まで浮かんでいた。
函館と東京は別じゃない、つながっているのだ。
自然や未来のことは、今を生きる全員に降りかかる。
そんなあたりまえに気づいて涙が出そうになるのは、料理人が、地元と地球、街と自然、歴史と未来を行ったり来たりしながら作っているからだと思う。

- Colz|コルツ
- 函館、東京、北イタリアで修業した佐藤雄也シェフが、2003年にオープン。2023年7月に函館市内で移転。街にありながら、土と木を感じる建物を得て、道南の自然を感じる『コルツ』の世界観が完成した。
-
北海道函館市宝来町34-7
TEL|0138-84-5858
営業時間|12:00-13:00L.O./18:00-20:00L.O.
定休日|日、月(変更の場合あり)
NEXT CHAPTER
新連載「僕らの新しいローカリズム」、スタートは北海道・函館編から。
石畳の坂道に洋館が建ち並ぶ港町風情と、雄大な自然が静かに溶け合うこの地に惹かれたつくり手たちを、全9回にわたってお伝えします。
次回は、3月25日
ー毎月、満月の日に新たな記事を更新
CHAPTER 06『清和の丘農園』 comming soon