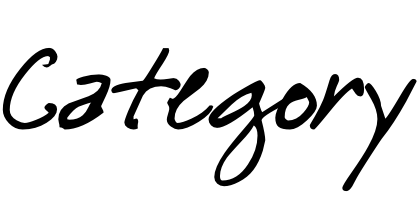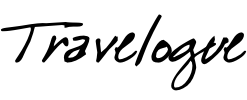 僕らの新しいローカリズム
僕らの新しいローカリズム

僕らの新しいローカリズム|石川 能登
半島という地形は魅力的だ。独立しているようでいて地は続き、
吹き抜ける風が、海の向こうから運んで きた種を落とす。
日本海に最も突き出した半島、能登。
北前船や京文化が種を落としたこの土地では、今また新しい人、戻る人、迎える人がひとつになって食文化の芽を育てている。
山から海へと巡る食、蔵と田が醸す酒、昇華された工芸品。
「能登の自然は時に厳しいけれど、それを癒やしてくれるのもまた自然」
傷ついた人々にさえそう感じさせてしまう、能登とはどんなところだろう?
写真/伊藤徹也 文/井川直子
CHAPTER 24『能登かき 宮本水産』
海の牡蠣を育てるのは、山
「能登の真牡蠣は、桜が咲く頃に美味くなる」
この言葉を聞いたから、4月に照準を合わせて訪れたのだ。
心痛む2024年を越えて、能登に再び咲く2025年の桜を見たい。そしておいしさの頂点を迎えるという、『
宮本水産
』の「能登かき」を食べてみたい。
4月、実際に空港から車で少し走ると、すぐに桜が現れた。というか、そこらじゅうでもう満開だ。海沿いの崖でも、田畑のあぜ道でも、里山でもあたりまえに。
能登半島が歌うように桜を咲かせている、その美しさに、希望を感じずにはいられない。
この桜の山を降りてきたところに広がる七尾湾で、育まれているのが「能登かき」だ。リアス式の海岸線を持つ七尾湾は南湾、西湾、北湾に分かれ、養殖業者の多くは西湾に集まっている。
だが宮本哲也さんが、妻の里子さん、息子の崇弘さんと営む『宮本水産』は、ちょっと外れた北湾にぽつんとあった。哲也さんの父が商売替えをして牡蠣の養殖と販売を始め、2025年で46年目になるという。
「この海には、川がないんですよ。〝こんなところで育つか〟って言われるような所で、親父が始めちゃった」
たしかに西湾ならば、3つの河川が流入してプランクトンなどの栄養分が豊富なうえ、水深も10メートル以内と浅い。一方で『宮本水産』のある北湾は河川がなく、水深も急に深くなる海だ。
「川がないと成長はたしかに遅いんです。でもその分、生活排水などの影響を受ける心配がない綺麗な海、ともいえる。牡蠣は生食するものなので、結果的にはよかったんですよね」
海の牡蠣を育てるのは、山である。
山の森や地表に落ちた雨が土中に滲み込み、地層によってろ過されながら栄養分を蓄えて、海へと流れ出るから。
だが、その栄養豊富な水を運ぶのは、なにも河川だけでなく、出口は河口だけでもない。地中を通る水、または地中から湧く水などもある。
『宮本水産』の「能登かき」を育むのは、そういった水が注がれる海だ。
「能登には大きい山がないんですよ。しかも昔、森と土を育てる落葉樹を切って、国の政策で杉をいっぱい植えてしまった。そのつけが今になって回ってきたのと、温暖化などの要因も重なって、ここ20年、牡蠣の成長は少しずつ悪くなっていると思います」
それでも七尾市の、ここ中島という地区は、山の手入れを極めて厚く行っているという。地主が私財を投じて植林し、またこれまでも宮本さんの父をはじめ地域の住民たちが山や森の手入れに参加してきた。
彼らが植えてきたのは、能登で「あて」と呼ばれる能登ヒバだ。材質が緻密で硬く、湿気にも強いため住宅用の建材として優れた樹木。そういう木は、やはり成長が極めてスローである。
「あてが成長して山が回復するまで、どのくらいの年数がかかるか。息子の代でも無理でしょうね。息子の次の代……どうだろうな。地主も代替わりするだろうし、今の志を継いでくれればいいけど」
能登の海は、里山と対を成す「里海」とも呼ばれ、宮本さんいわく「半島の自然は循環している」。人間もまた自然の一部。自分たちがひずみを作ってしまったら、そのつけは自分たちや、その子孫たちに巡り戻ってくる。
殻からむいても生きている
人の手で再生されゆく山と、綺麗な海で育つ『宮本水産』の「能登かき」。
ひと足早く『
Villa della pace
』のディナーで味わった、その料理は
CHAPTER 22
で見ていただくとして、ここでは生をストレートに食べさせてもらった。
殻の上に膨らんだ身が載っている。「能登かき」は、このぷりっと盛り上がったスタイルが身上。身が真っ白ならなお、おいしい証拠だ。
ひと口でちゅるっと流し込めば、潮の味と独特のえぐ味が広がる。噛むうちにじわじわと湧き出る甘み、後を引くミネラル感、こっくりとした濃厚さ。
「僕はフルーツだと思う。うちの牡蠣はやっぱり甘い」
崇弘さんは生の牡蠣が大好きで、商品にならなかったハネモノを毎日のように食べているという。それでもまったく飽きないのは「おいしい」うえに、日によって味わいが微妙に変わるから。
牡蠣の味は海の状態を映し、日々刻々と成長する過程でも変わる。
真牡蠣の産卵は6〜7月。そこへ向かって栄養価を蓄えていくのだが、産卵直前には落ちてしまう。栄養価、つまりおいしさの素を溜め込んだピークは、だから4〜5月の桜の時季に重なるわけだ。
「昔は七夕くらいに産卵していたんですけど、近年は温暖化でバラつくようになりました。ゴールデンウィークにすごい暑くなったりすると、早く産卵することもあります」
ちなみに夏は夏で、今度は岩牡蠣のシーズンに入る。
養殖は、種牡蠣(稚貝)をホタテのバグ(貝殻)につけてロープにつなぎ、海に沈めたまま1年半〜2年成長を待つ。
そこまでは大体同じだが、宮本さんは出荷の1カ月ほど前に一度引き揚げ、フジツボや藻といったさまざまな付着物を取り除き、再び海に戻すという手間をかけている。
「殻を食べるわけじゃないんだけど、やっぱり綺麗なほうがいい」
ラスト1カ月、寝かせて身をととのえてから満を持して揚げる。人間の仕事は、牡蠣が揚がってからが勝負である。
作業場を見せてもらうと、崇弘さんが水圧でざっと付着物を取り、さらに里子さんやスタッフが手作業で取り除いていた。硬くへばりついた付着物を、殻を傷つけずに取る。
殻に気を遣うのは、昨今、「殻付き」の需要が増えたからだ。
殻のまま届くほうが新鮮なイメージ?じつは職人の技術次第では、「むき身」のほうが鮮度を保てるという。
「殻付きは、海水(塩水)から揚げた時からだんだん痩せていきますよね。でもむき身は塩水の中に浸かっているので、殻から生きたまま身をむく技術さえあれば、塩水のなかでも生きています」
その高い技術を持つのが里子さん。目を見張るスピードで殻をむき、塩水に落とされたむき身は気持ちがよさそうだ。
夏から冬までは、岩牡蠣のシーズン
『Villa della pace』の平田明珠(めいじゅ)シェフが、『宮本水産』に絶対の信頼を寄せるのは、この品質に対する誇りである。
「納得のいかない牡蠣は絶対に売ってくれない。それはすごくありがたいことで、いいものしか薦めないと知っているから、僕も自信を持って料理に使えるんです」
その言葉に、里子さんは申し訳なさそうに答えた。
「お客さんは、どんどん頂戴って言ってくださるんですけどね」
顧客らが「どんどん頂戴」と注文を寄せるのは、2024年があまりに厳しかったからだ。
1月の能登半島地震では、揚げたてを生のまま食べたり、焼き牡蠣などにもできる食堂が全壊した。ただ、海底が揺さぶられて栄養分が撹拌され、牡蠣にとってはいい材料もあるにはあったのだ。
追い打ちをかけたのは、9月の豪雨である。
「土砂が流れ込んで海が濁り、大雨の後は1週間くらい岩牡蠣が取れんかった。そのうえ海水温も急激に下がって、びっくりした岩牡蠣が産卵してしまったんですよ。まだまだ出荷できる状態だったのが全部売れなくなった。その年はもう、商売になりませんでした」
2025年に入ってようやく再開できた「能登かき」である。
売れるものなら売りたいのはひとしおだろうに、それでも品質のハードルを下げないことはなかなかできることじゃない。
でも、だからおいしいのだ。
今年も7月から、岩牡蠣のシーズンが続行中。一気に産卵する真牡蠣と違い、岩牡蠣は秋から冬にかけてゆっくり、徐々に産卵していくのが特徴だから長く食べられる。
「岩牡蠣は3年から5年育てるんです。今も海のなかで育ってて、もういい状態になってますよ」

- 能登かき 宮本水産
-
七尾湾で育て、水揚げしたての「能登かき」のむき身と殻付きを販売。以前は食堂も経営していたが、震災により全壊し(再建計画中)、現在は真牡蠣(春)と岩牡蠣(夏〜冬)の養殖と出荷を行う。日本全国へ発送可。家族による少量生産のため、注文は電話でのみ受付。
石川県七尾市中島町外イ-29
TEL|0767 66-0002
受付時間|9:00〜16:00
NEXT CHAPTER
「僕らの新しいローカリズム」石川県・能登編は全6回。
第4回は、『月とピエロ』
中能登の里山に建つ『月とピエロ』は、パン好きが全国から訪れるブーランジェリー。長屋圭尚(ながやよしひさ)さんが薪窯で焼く天然酵母パンと、妻・由香里さんによる焼き菓子のお話です。
次回の公開は、2025年10月7日ハンターズムーン。毎月、満月の日に新たな記事を更新します。
CHAPTER 25 comming soon『月とピエロ』